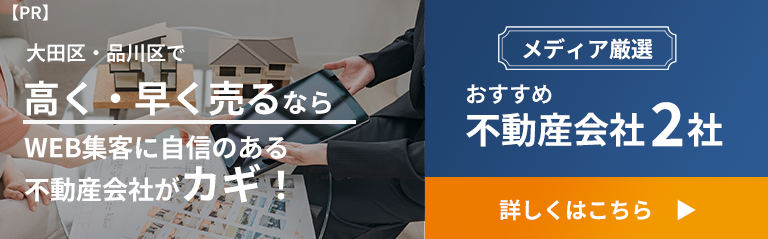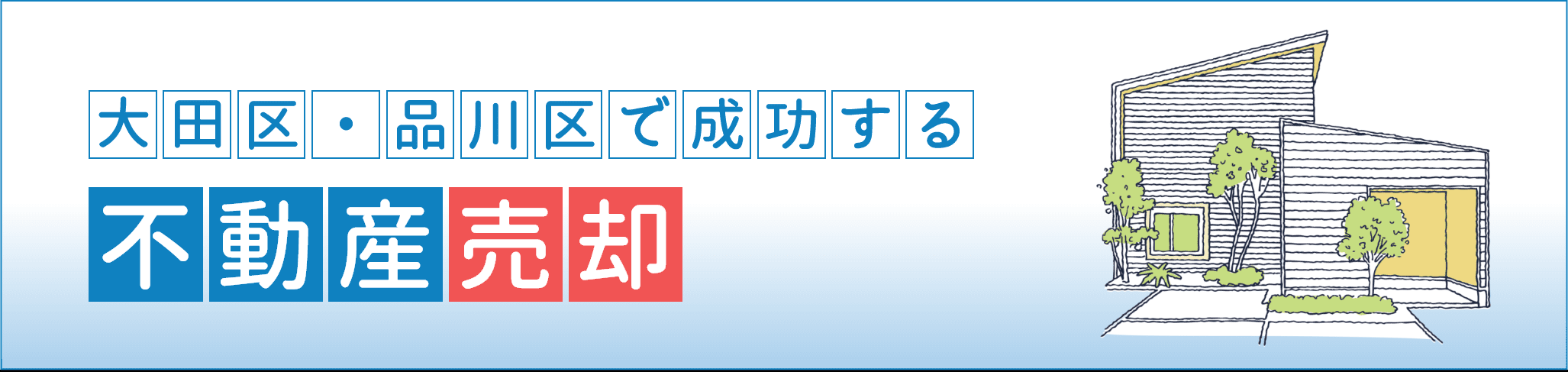不動産売却と「リースバック」の税務・法務基礎

不動産を売却する方法の一つとして、近年注目されているのがリースバックです。これは自宅を売却したうえで、買主と賃貸契約を結び、同じ住まいに住み続けられる仕組みを指します。
高齢者が老後資金を確保する手段や、急な資金需要に対応する方法として利用されることが増えていますが、その一方で、税務上の手続きや法務手続きに関して不明点が多いと感じる方も少なくありません。
本記事では、リースバックを活用した不動産売却において押さえておきたい「税務面での注意点」と「契約手続き上の法務面での要点」を詳しく解説します。
まずは「税務上の注意点」として、リースバックが譲渡所得の計算や特例適用にどう関わるか、リース料との兼ね合いでどのような申告が必要になるのかを整理します。次に「法務手続きと契約条件」に触れ、賃貸借契約の期間や更新条件、再購入オプションの有無、さらには専門家への相談がなぜ重要なのかを考察します。
一見するとシンプルに思えるリースバックですが、「自宅を売りつつ賃借人として住み続ける」という特殊な構造上、譲渡所得の扱いや契約の締結手続きが通常の売却と大きく異なります。
そこで本記事を通じて、より有利な条件でリースバックを利用し、売り主・買主双方が安心できる取引を目指す知識を身につけていただければ幸いです。
目次
税務上の注意点

リースバックを活用して自宅を売却した場合、「所有権を買主に譲渡し、同時に賃貸借契約を結んで住み続ける」という特殊な構造が生まれます。
しかし、法律上は売却(譲渡)として扱われるため、譲渡所得が発生する可能性があり、通常の不動産売却と同様に所得税や住民税の課税対象となり得るのです。さらに、売却後も家賃(リース料)を支払い続ける立場になるため、資金調達できるメリットと引き換えに毎月の負担が発生する点で、家計管理が重要になります。
本節では、まず譲渡所得計算・控除を整理し、続いてリース料との兼ね合いによる家賃支出と税負担の関係を考察します。
譲渡所得計算・控除

1. リースバック時の「譲渡」としての扱い
リースバックは、自宅を買主に売却しながらも自身は賃貸借契約を締結して住み続ける手法です。多くの方が「住み続けるのなら売却益は発生しないのでは?」と感じるかもしれませんが、法的には所有権の移転が生じているため、「不動産譲渡」に該当します。
•売り主(元所有者):物件を手放す代わりにまとまった資金を得る一方、買主と結んだ賃貸借契約に基づいてリース料を払います。
•買主(投資家・不動産会社など):物件を取得し、売り主から毎月の家賃収入を得ます。
その結果、売り主には譲渡所得が生じる可能性があり、譲渡所得税(所得税および住民税)の課税対象となります。もし残ローンを完済しても譲渡所得が残るようなケースでは、確定申告で適切に納税しなければならない点に注意が必要です。
2. 譲渡所得の計算フロー
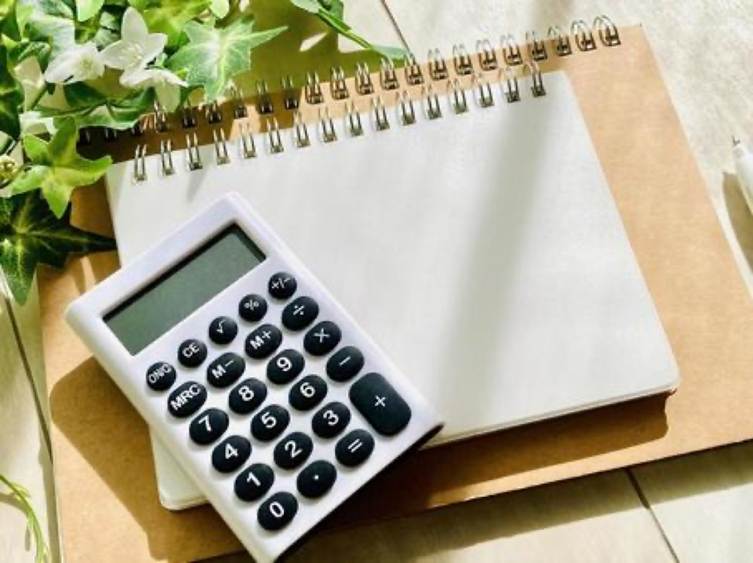
譲渡所得は、下記の式で計算します。
譲渡所得 = 譲渡価格 - (取得費 + 譲渡費用)
•譲渡価格:リースバックで設定された売却金額
•取得費:購入時の物件価格や仲介手数料など。相続などで不明なら「概算取得費5%」を適用可
•譲渡費用:今回の売却時にかかった仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用など
リースバックの場合、買主はリース料から収益を得るため、売却額(譲渡価格)が市場相場より低く設定されることが多いです。
投資リスクを考慮して安めの金額で買い取る投資会社もあるため、譲渡所得が思ったより少なくなる可能性がありますが、逆に取得費が極端に低いなどの理由で課税額が高まることもあるので要注意です。
3. 特別控除や減税制度の適用可否

居住用不動産を売却する場合、3,000万円特別控除などの優遇税制が利用できる可能性があります。リースバックでも、基本的に「住んでいた自宅」の売却とみなされるケースが多く、これらの特例を活用できる見込みが高いです。とはいえ、以下の点をチェックしておく必要があります。
•マイホーム特例の要件
所有期間や居住期間に関する細かい要件を満たさないと、特別控除や軽減税率が使えない場合があります。
•自宅と認められないケース
一部を賃貸に回していた、セカンドハウス扱いなどの場合は控除対象外となるリスクがあります。
•長期譲渡所得の軽減税率
所有期間が10年以上の居住用財産を売却するとき、軽減税率が適用されるパターンがあります。リースバックでも同じく該当するかどうかの確認が必要です。
こうした控除や優遇が使えるかどうかは、税理士や不動産会社のサポートを受けながら判断するのが無難です。誤って特例を適用して後から否認された場合、多額の追徴課税を課される恐れがあります。
4. 事例:想定外の譲渡所得課税

リースバックで自宅を売却した結果、ローン完済には成功したが、取得費が予想以上に低く計算され(相続や古い購入のため)、譲渡所得が大きくなって多額の税金が発生してしまったという事例もあります。
とくに旧耐震の築古物件を長期間持ち続けていた場合、購入時の金額が安かったうえに、現在の査定価格がそれなりにあるため「当初想定以上の譲渡所得税を負担する」ケースが生じることがあるのです。
契約前に売り主自身が確定申告シミュレーションをしていなかったため、後から資金計画が狂うという問題が起きることがあります。
リース料との兼ね合い

リースバックでは売却後も同じ家に住める利点がある一方、売り主が賃借人となってリース料(家賃)を払い続ける必要があります。この毎月の出費が、家計にどう影響するか、さらに税務申告の面ではどう扱われるかが次の焦点です。
1. 毎月のリース料(家賃)の設定
1.家賃相場と投資会社のリスク見込み
リースバックで設定される家賃は、一般的な賃貸相場と同程度か、あるいは投資会社がリスクを高めに見積もりやや高い家賃を設定することもあります。
逆に、売り主の資金状況を考慮して安めに設定されるケースもありますが、その場合は売却額が安くなるなど、どこかでバランスが取られる形になるでしょう。
2.高齢者・収入不安定層の悩み

毎月の家賃支払いが収入を超えてしまうと、住み続けるのが難しくなり、結局退去を余儀なくされる事態も起こり得ます。老後資金の確保目的でリースバックを選択したものの、家賃負担が大きく生活が苦しくなるケースが散見されるため、売り主は事前に家計シミュレーションを行っておくべきです。
2. 税務上のリース料と損益通算
1.家賃支出は通常経費にならない
リースバック後の家賃支払いは、基本的に「住居用賃料」として所得控除の対象外です。事業経費として扱うのは難しく、譲渡所得から相殺することもできません。
2.譲渡所得の計上時期
リースバック契約が締結された時点で譲渡所得が発生しますが、その後の家賃支払いはこの譲渡所得を減らしてくれるわけではありません。したがって、「譲渡益を得たのに家賃で帳消し」という発想は成り立たない点に要注意です。
3.住民税・健康保険料への波及

売却年の所得が増えると、翌年度の住民税や国民健康保険料なども高騰する可能性があります。高齢者や定年退職者にとっては、「税金+家賃の二重負担」が家計を圧迫するリスクとなり得ます。事前に税理士に相談し、最適な申告スケジュールや節税対策を検討することが重要です。
3. リース料見直しと長期的家計管理
リースバックの賃貸借契約には、契約期間満了時の更新や家賃改定についての条項が盛り込まれます。多くのケースでは2年ごとの契約更新を想定し、家賃改定の権限を貸主が持つ形となるため、将来的に家賃が値上げされることも考慮しなければなりません。
•長期居住か短期利用か
売り主が老後まで住み続けたい場合、定期借家契約では契約満了で退去を求められる可能性が高いため、更新の仕組みを明示しておく必要があります。
•再購入特約の存在

リースバック契約に再購入オプションが付いていると、将来収入が増えたときに物件を買い戻せる可能性がありますが、買い戻し価格が契約時より大幅に上昇しているケースも。これを知らずに期待していると資金計画が狂うので、書面で厳密に取り決めることが欠かせません。
リースバックによる不動産売却は、自宅を手放してまとまった資金を得ながら、引き続き賃借人として住み続けられるメリットがあります。
しかし、法的には「売却(譲渡)」とみなされるため、譲渡所得税や住民税の課税対象となる点には十分注意が必要です。譲渡所得の計上時には取得費や譲渡費用を正しく把握し、3,000万円特別控除や長期譲渡所得の軽減税率が適用できるかどうかを確認しましょう。
さらに、リース料(家賃)の支払いは税務上で経費にならず、家計に重い負担となる可能性があります。譲渡益がある程度見込まれる一方で、その年の所得が増加することで住民税や健康保険料が翌年に大幅に上がるケースもあるため、老後資金などを念頭に置いた事前のシミュレーションが欠かせません。
特に高齢者がローン完済のためにリースバックを選ぶ場合、家賃が予想以上に高く設定されることもあるため、契約書の内容を丁寧に確認し、税理士や不動産会社に相談しながら計画的に進めることがリスク回避のカギとなります。
◯あわせて読みたい記事
不動産売却ではどんな費用がかかる?利用できる控除の種類や注意点を紹介
法務手続きと契約条件

リースバックを利用する際には、単に「自宅を売って賃貸として住み続ける」だけでなく、法務面で特有の手続きや契約条件をしっかり把握しておく必要があります。通常の不動産売買なら、引き渡しが終われば売り主は物件に関与しなくなるのが一般的です。
しかし、リースバックでは売り主が今度は“借主”として居住を続けるため、売買契約と賃貸借契約を同時に取り結ぶという特殊な構造が生まれます。
この章では、まず「契約期間・更新条件」を中心に、賃貸借契約の期間や更新ルールがどのように設定されるのかを解説し、その後に「専門家相談でリスク軽減」として、弁護士や司法書士など専門家のサポートがなぜ重要なのかを考察します。
契約期間・更新条件

リースバックの最大の特徴は、「物件を手放しても同じ住まいに住める」という点です。しかし、この「どれくらい住めるのか」という肝心の部分が、契約内容によって大きく変わります。
売買契約と同時に結ばれる賃貸借契約の期間設定や更新方法を誤ると、後になって「こんなはずじゃなかった」というトラブルになりやすいのです。以下では、契約の種別や期間設定など、押さえておくべきポイントを詳しく見ていきます。
1. 定期借家契約か普通借家契約か
リースバックでは、定期借家契約が採用されるケースが一般的です。定期借家契約の場合、契約期間が終わると、原則として更新がなく、貸主(買主)が契約どおりに退去を要求すれば、借主は退去せざるを得ません。
これは投資家や不動産会社が、「いつまでも住み続けられると売却・再投資の機会を失う」というリスクを敬遠するからです。
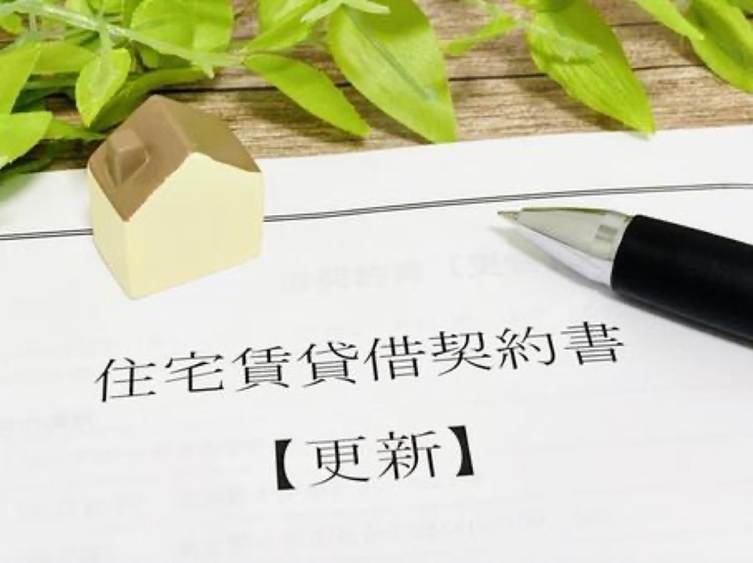
一方で、普通借家契約を選択すれば、契約満了時に更新が認められる可能性が高いですが、リースバックを扱う買主側が普通借家契約に応じるかは別問題です。売り主(借主)の視点では、普通借家契約なら長期的に住めるメリットがありますが、投資家は流動性を確保しづらいデメリットを抱えることになります。
したがって契約形態を決める際には、「どのタイプを選べるか」「選ぶなら家賃や売却額にどう影響するか」を慎重に検討する必要があります。
2. 契約期間の長さと更新有無
一般的なリースバックの契約期間は2年~5年程度が多いですが、売り主の意向や買主の事情によっては10年という長期契約になるケースもあります。特に高齢者が「終の住処として住み続けたい」と考える場合、短期の契約では不安が大きいものの、長期契約はその分リース料が高めになる可能性があるため、家計とのバランスを吟味しなければなりません。
•更新時の家賃改定

賃貸契約には家賃改定ルールが含まれるのが一般的です。物価上昇や相場変動を踏まえ、更新時に家賃が引き上げられる可能性があります。これを固定するか、相場に合わせるのかを契約書で明示しておかないと、数年後に大幅値上げを受けて住み続けられなくなるリスクがあります。
•契約書への明記
「更新手順がどうなっているか」「更新時に双方の合意が必要なのか」「自動更新はあるのか」といった要素を細かく文書化することで、売り主と買主の認識差を最小限に抑えられます。
3. 「終身住み続けられる」とは限らない
リースバックに対して、「家を売っても死ぬまで住める」という漠然としたイメージを抱いている人がいますが、実際には契約書で“終身”を明記しない限り、確約されないのが実情です。終身契約を提示するリースバック商品も存在しますが、その分家賃が割高だったり、途中退去や解除条件が通常の定期借家より厳しかったりします。
•「終身契約」か「契約期間終了で退去」か
終身契約であれば長期的に安心して住めますが、買主がなかなか見つからない、あるいは見つかっても家賃や売却額が売り主にとって不利になる可能性も。売り主が老後の住居確保を重視するのか、短期的資金ニーズを重視するのかで選ぶ契約内容が変わってきます。
•家賃負担が永続的に続く

終身契約であっても、家賃の支払いは基本的に続きます。収入が減ったり医療費が増えたりした際に家賃が支払えなくなると、結果として退去リスクが発生します。契約書に「家賃滞納が続いた場合は契約解除」と明記されるケースも多いので、注意が必要です。
4. 再購入特約の有無
リースバックには、将来的に物件を買い戻せる「再購入オプション」が付く場合があります。これは、売り主(借主)が経済状況を立て直したり、再び資金調達できたときに物件を再取得できる仕組みです。ただし、以下の点が争点になりやすいため、契約書で明確に定めましょう。
•買い戻し価格の算出方法

当初の売却額に一定の利息やコストを加算するか、査定会社が当時の時価を再評価するかなど、多様な方法があります。これをあいまいにすると、後日「こんなに高く買い戻すのは想定外」という対立が起きやすいです。
•買い戻し期限
一定期間内であれば買い戻し可とするのか、期限を定めずに随時可能とするのかによって、投資家(買主)のリスクも変わります。投資家が制限を厳しくしたがる場合もあれば、売り主が柔軟性を求めるケースもあります。
専門家相談でリスク軽減
リースバックは普通の不動産売買と比べて契約内容が複雑になりやすく、さらに毎月の家賃負担や再購入特約など、多面的なリスクが介在します。
こうした背景から、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談して契約書や権利関係を整理することが、リスク軽減の大きなポイントとなります。
1. 弁護士の役割:契約書レビューと紛争防止

•契約書の法的整合性チェック
弁護士は、リースバック契約特有の条項(定期借家か普通借家か、更新ルール、再購入特約など)を法的観点で確認し、売り主側が不利になりすぎないよう助言してくれます。
•トラブル発生時のサポート
リースバック契約後に家賃滞納や契約更新をめぐる争いが発生した場合も、弁護士が早期に介入すれば和解や交渉がスムーズに進む可能性が高く、長期紛争を防ぐ効果が期待できます。
2. 司法書士の役割:登記関連・書類整備
•所有権移転登記、抵当権抹消など
リースバックでは通常の売却と同様に所有権移転登記を行います。さらに住宅ローンが残っていれば抵当権抹消などの手続きも必要です。司法書士がこれらを一括して進めることが可能です。
•相続登記の未完了や共有者の存在に注意
売却前に相続登記が済んでいない、兄弟で共有しているなどの場合、リースバックに入る前提として登記を整理しなければならないこともあります。司法書士が権利関係を把握し、スムーズに進めるサポートを担います。
3. 税理士の役割:税務申告と事前シミュレーション

•譲渡所得や特例の確認
前章で述べたように、リースバックによる譲渡所得がどう計算されるか、3,000万円特別控除や長期譲渡所得の軽減税率が適用可能かなど、細かい要件をプロの視点でチェックできるのが税理士です。
•家賃支払い・住民税負担のバランス
譲渡所得が増えると翌年度の住民税や国民健康保険料が上昇し、それに加えて家賃支払いが重なって家計を圧迫する恐れがあります。事前に税理士がシミュレーションすることで、売り主は必要なキャッシュを確保するプランを立てやすくなります。
4. 不動産会社のフォロー体制
•リースバック専門の仲介会社
リースバックサービスを手掛ける不動産会社は、アフターフォローや買主との交渉代行を行うプランを提供している場合があります。売り主が一人で投資家と交渉するのはハードルが高いため、仲介会社に対応を任せられるかどうかを契約前に確認すると安心です。
•トラブル時の仲裁役

不動産会社が売却契約後にも相談を受け付けてくれれば、家賃交渉や契約更新時のトラブルを防ぎやすいです。ただし、口約束だけでなく、実際にサポートを行う範囲や料金体系を明示してもらうことが必要になります。
リースバックは不動産を売りながら同じ家に住み続けられる方法として注目されていますが、法務面では売買契約と賃貸借契約の両立が必要になるため、契約書が複雑化しがちです。
特に、契約期間を定期借家とするか普通借家とするか、更新時の家賃改定ルール、終身契約や再購入特約をどう設定するかなど、細かい条項を明確にしないまま契約を進めると、後から「契約が終われば退去しなくてはならない」「買い戻し価格が想像以上に高かった」といったトラブルに発展する可能性が大いにあります。
こうしたリスクを最小限に抑えるには、弁護士や司法書士、税理士など専門家の助力が不可欠です。弁護士は契約書の合法性や紛争防止の観点からレビューを行い、司法書士は登記手続きや法的権利関係の整理をサポート、税理士は譲渡所得や家賃負担を踏まえたシミュレーションを行ってくれます。
結果として、売り主はリースバックのメリットを活かしながらも、老後資金や生活資金を安定的に運用できる可能性が高まるのです。
◯あわせて読みたい記事
まとめ:法税知識でリースバックを有効活用
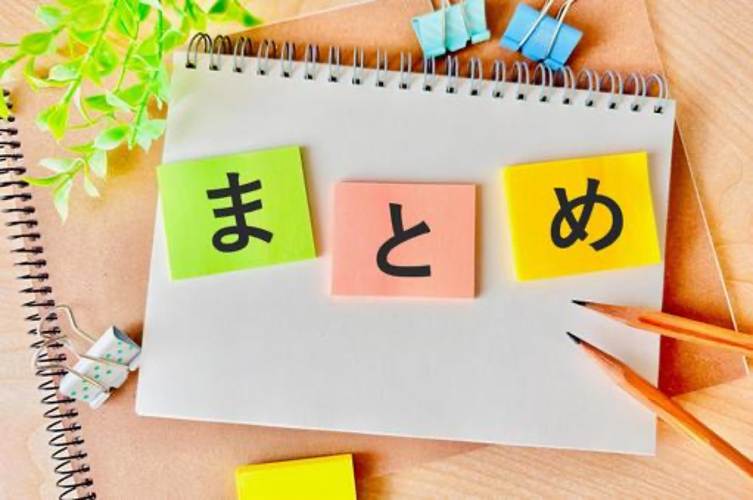
リースバックは、自宅を売却して資金を得つつ、引き続き住み続けられる利点がありますが、その一方で法務手続きや契約条件が複雑化しがちなのが実情です。
売買契約と同時に賃貸借契約を結ぶため、契約期間や家賃改定のルール、更新時の方針などを細かく設定しておかなければ、将来的に「住み続けるつもりが契約終了で退去せざるを得ない」などのトラブルを招くリスクがあります。
また、再購入オプションの有無や買い戻し価格の決定方法なども、事前に書面化しないと後で争いの火種となりかねません。
こうしたリースバック特有の法務リスクを回避するためには、弁護士や司法書士など専門家の力を借りて契約書を精査したり、登記手続きを正確に進めたりすることが大切です。さらに税理士に相談して譲渡所得や控除の取り扱いを整理すれば、誤った課税を防ぎながら住み慣れた家での生活を維持できます。
売却後も安定した住居を確保し、資金ニーズと生活ニーズを両立させるために、契約前の段階でしっかりと専門家を交えた準備をしておきましょう。
◯あわせて読みたい記事