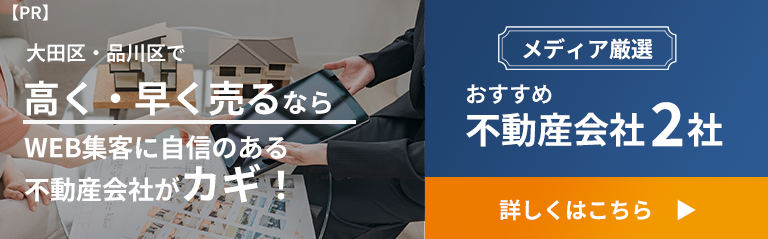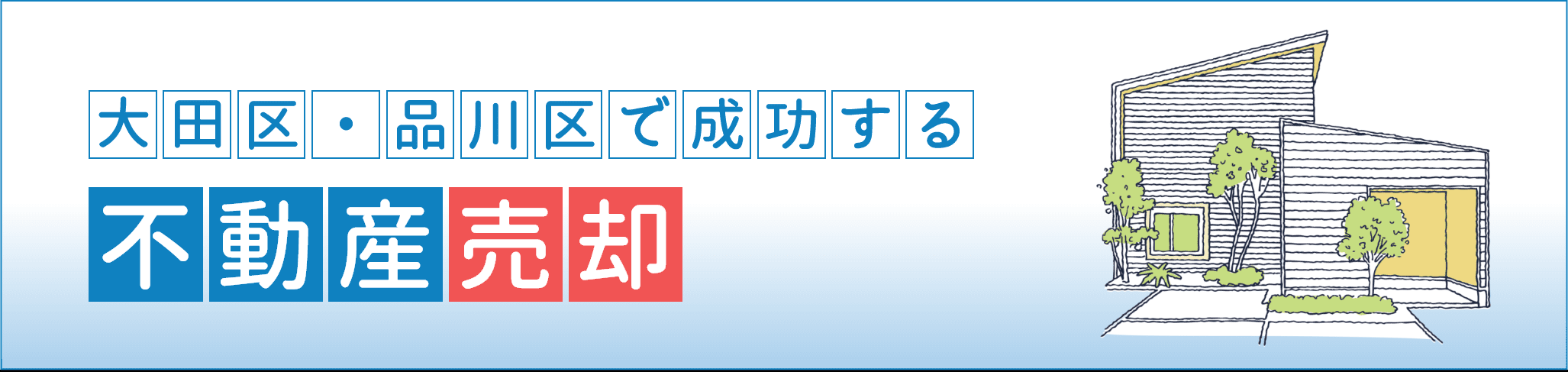不動産売却時の諸費用を徹底解説!税金・手数料・引越し費用まで

不動産を売却する際、仲介手数料や譲渡所得税、印紙税といった基本の費用だけでなく、引越し費用や不用品処分費など、思わぬ出費が重なる場合があります。こうした諸費用を把握していないと、「売却益が予想より少なくなった」や「引越し費用まで予算に組み込んでいなかった」といった失敗を招きがちです。
本記事では、売却時に発生する費用の全体像をわかりやすくまとめました。読者の皆さまが余裕をもって正確な資金計画を立てられるよう、見落としがちな項目や節約のコツも紹介しています。最後までお読みいただき、無駄な出費を抑えてスムーズに不動産売却を進めましょう。
目次
発生する主な費用項目
不動産を売却する際、まず押さえておきたいのが「どのような費用が、いつ、いくらかかるのか」という点です。売却益を予測しても、諸費用の見積もりを誤ると、最終的な手取り金額が大きく変わってしまう恐れがあります。
そこで本セクションでは、仲介手数料、印紙税、そして譲渡所得税という、ほぼ確実に発生すると考えられる3つの主要費用について詳しく解説します。これらの費用がどう算定されるのか、支払うタイミングはいつなのかを理解しておくことで、資金計画を立てやすくなり、急な出費に悩まされるリスクを減らせるでしょう。
不動産の売却活動を始めると、一般的には不動産会社との媒介契約や契約書の作成、買主との売買契約、決済といった流れを踏むことになります。その各段階で手数料や税金が発生するため、「契約を結んだはいいが、支払いが一度に重なって予定外の出費になった」という失敗例も少なくありません。特に印紙税や譲渡所得税は税制改正などの影響を受ける場合があるため、最新の情報を定期的にチェックしておくことも大切です。
ここでは、まず仲介手数料の計算方法と発生タイミング、次に印紙税の基礎知識と注意点、最後に多くの方が戸惑いやすい譲渡所得税の概要について順に説明します。いずれも高額な費用になりがちなので、「売りに出す前」の早い段階から概要をつかみ、シミュレーションしておくと良いでしょう。
仲介手数料・印紙税・譲渡所得税
不動産売却に伴う費用の中でも、頻度が高く金額も大きいとされるのが、仲介手数料・印紙税・譲渡所得税の3つです。どれも売買契約を結ぶ際や、売却後に手続きを行う際に発生する費用ですが、それぞれの算定方法や支払い時期が異なります。以下で一つひとつ掘り下げていきましょう。
1.仲介手数料
•不動産会社への報酬
不動産会社(仲介業者)は、売却希望者の代わりに物件の宣伝や買主との交渉、契約書類の作成サポートなどを行います。その対価として発生するのが仲介手数料です。
•上限計算式
一般的には法律(宅地建物取引業法)によって上限額が定められており、という式で算出されます。ただし、売却価格が400万円以下の場合は別の計算方法を用いるので注意が必要です。
•支払いタイミング
仲介手数料は、売買契約締結時と決済(引き渡し)時に分割して支払うことが多いです。全額を決済時にまとめて支払う契約形態もあり、契約形態や不動産会社との取り決めによって異なります。
•消費税の加算
手数料には消費税が上乗せされる点も見落としがちです。たとえば3,000万円で売却した場合、(3,000万×3% + 6万)=96万円に消費税を加えた金額が上限手数料となります。
2.印紙税
•売買契約書に貼付する印紙
不動産売買契約書は、法的に有効な文書として扱われるため、印紙税法に基づいて所定の印紙税を納付しなければなりません。具体的には売買契約書の1通ごとに印紙を貼り、消印をする形で納税が完了します。
•税額は売却価格に応じて変動
印紙税は契約金額によって段階的に異なる税率が設定されており、たとえば1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円(あるいは軽減措置期間中は減額される場合も)など、金額帯に応じて税額が決められています。税制改正で軽減措置が延長されることもあるため、最新情報をチェックしましょう。
•納付タイミング
売買契約書を作成する段階で必要となります。印紙税を貼らない契約書は正式には効力を得られない可能性があり、トラブルを回避するためにも売買契約締結時には必ず印紙を貼っておくことが大切です。
3.譲渡所得税
•売却益に課税される税金
不動産を売却して譲渡益(売却益)が発生した場合、その利益部分に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は所得税と住民税の合計であり、状況によって復興特別所得税が加わる場合もあります。
•短期・長期の違い
不動産を所有していた期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得となり、適用税率が大きく異なります。一般に長期のほうが税率が低いため、「あと少しで5年を超えるから待ってから売る」という計画を立てるケースもあります。
•支払いタイミング(確定申告)
譲渡所得税は売却した翌年の確定申告時に申告・納税するのが原則です。売却益が出なかった(または損失が出た)場合でも、特例を使って節税ができる可能性があるため、一度は申告の要否を確認すると良いでしょう。
こうした主要費用は、売却を進めるうえで必ず頭に入れておくべき項目と言えます。なかでも譲渡所得税は、物件の取得費や売却時の費用をどう扱うかで大きく額が変わるため、しっかりと理解しておくことが大事です。
次のセクションでは、譲渡所得税の計算式を具体的に示し、取得費や譲渡費用に含まれるものについてわかりやすく解説します。所有期間による短期・長期の税率差や、減価償却の扱いなど専門的な要素も含まれるため、必要に応じて税理士などの専門家に相談すると安心です。
譲渡所得計算式のポイント
譲渡所得税を正しく算出するには、まず「譲渡所得」を求める必要があります。基本の計算式は以下のとおりです。
ここでは、譲渡価格が実際に売却した金額を指します。そして、その金額から物件を購入・取得する際にかかった諸経費(取得費)や、売却のためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いたものが「譲渡所得」となるわけです。この譲渡所得に対して、短期・長期どちらに該当するかを確認し、所得税と住民税を合わせた税率を乗じて納税額を算出します。
1.取得費に含まれる具体例
•購入時の物件代金
•購入時の仲介手数料や登記費用、司法書士報酬などの諸経費
•リフォーム費用(ただし資本的支出に当たるもの)
•減価償却の対象となる建物部分の耐用年数に応じた減価償却費
もし取得時の詳細が不明な場合、「概算取得費」を用いて譲渡価格の5%を取得費として計上することが認められていますが、実際の取得費が大きい人がこれを用いると損をする場合があります。
2.譲渡費用に含まれる具体例
•売却時の仲介手数料
•印紙税や登記費用、測量費用
•契約解除時に支払った違約金(特定の条件下で)
•広告宣伝費(売却のために出した広告があれば)
逆に、引越し費用やリフォーム費用の一部などは譲渡費用に含められないことがあります。どこまでが譲渡費用に該当するかは個別のケースによるため、曖昧な場合は税理士や不動産会社に確認 することが大切です。
3.取得費が不明な場合
古い物件を相続したり、購入時の書類を紛失していたりして取得費が明確でないケースも珍しくありません。この場合、前述の概算取得費(譲渡価格×5%)を使うことができますが、本来の実際の取得費が大きければ損をする可能性があります。逆に実際の取得費が小さい場合は概算のほうが有利になることもありますが、税務調査で証明できなければトラブルのもとです。
4.減価償却の考え方
建物の購入額については、所有期間中に減価償却が行われたとみなすルールがあります。簡単に言えば、建物は経年によって価値が下がるため、購入時の金額から減価償却費を差し引いた金額が「現在の取得費」として扱われます。
•例: 建物価格1,000万円、耐用年数30年の物件を10年後に売る場合、ある程度の年数分を償却して取得費を圧縮しなければならない。
•このため、建物の購入時価額や耐用年数がわかる資料がないと計算が複雑になるため、購入当時の契約書や明細をよく保管しておくことが重要です。
5.短期譲渡所得・長期譲渡所得による税率の違い
•短期譲渡所得(所有期間5年以下): おおむね39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)が適用される。
•長期譲渡所得(所有期間5年超): おおむね20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が適用される。
所有期間の判定は、取得した日(契約日ではなく登記日や引渡日の扱いに注意)から売却した日までの通算で数えます。1月1日時点で丸5年を超えているかどうかが基準になるため、売却タイミングを慎重に選べば納税額が大きく変わることもあります。
アドバイス: 上記のように、譲渡所得税の計算には専門的な知識が求められる場面が多々あります。とりわけ減価償却費の控除や概算取得費の選択、相続物件の取得費扱いなどは複雑です。「いくら税金を納めればいいか分からない」「取得時の情報がなくて困っている」という場合は、税理士や信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。申告ミスや漏れがあると後日ペナルティを受ける可能性もあるため、重要な手続きであることを意識しましょう。
追加でかかる可能性がある費用
不動産を売却する際、仲介手数料・印紙税・譲渡所得税といった「主要な諸費用」は多くの方が事前に把握しているかもしれません。しかし、実際に売却を進める過程では、ローン残債清算や抵当権抹消、そして不用品処分・引越しにかかる費用など、思わぬ出費が発生することも少なくありません。
こうした費用は必ずしもすべての売却ケースで生じるわけではありませんが、発生した場合には数万円から数十万円程度の追加コストとなる可能性が高いです。特に「ローン返済がまだ残っている」「大規模な断捨離を伴う引越しになる」などの状況であれば、想定外の出費が売却計画を揺るがすこともあるでしょう。
そこで本セクションでは、「追加でかかる可能性がある費用」として、まずローン残債清算費用と抵当権抹消費用について解説します。これらは、住宅ローンを利用している方にとってほぼ不可避の費用と言えます。さらに、大切なポイントとして、不用品処分や引越しにかかる費用も取り上げます。売却後に引越しを予定しているなら、荷物のボリュームや時期によって料金が大幅に変動するため、早めの計画が不可欠です。
「そんなこと知らなかった」「あれもこれも費用がかさむ」という状況を避けるためにも、あらかじめ追加費用をリストアップしておき、大まかな見積もりを立てましょう。以下では、ローン残債の清算や抵当権の抹消手続きにまつわる注意点に加え、不用品処分や引越しに関する具体的なコストと節約のコツをまとめています。読者の皆さまが、売却による最終的な収支をきちんと把握し、スムーズに取引を進められるよう役立てていただければ幸いです。
◯あわせて読みたい記事
不動産売却ではどんな費用がかかる?利用できる控除の種類や注意点を紹介
ローン残債清算費用・抵当権抹消費用
不動産売却時にまだ住宅ローンを完済していない場合、売却益を使ってローンを清算する必要があります。さらに、ローンを組んでいる物件には抵当権が設定されていることが多いため、引き渡し前にその抵当権を抹消しなければ、買主にとっては「担保付きの物件」となり契約を結べません。ここでは、ローン残債の清算時のポイントと、抵当権抹消に必要な費用・手続きについて詳しく見ていきましょう。
1.ローン残債清算費用
•繰上返済手数料
売却によって得た資金を使い、ローンの一括返済(繰上返済)を行う場合、銀行によっては繰上返済の手数料がかかります。ネット銀行や一部の金融機関では繰上返済手数料が無料のところもありますが、数万円程度の費用が生じるケースが一般的です。また、繰上返済にあたっては金利タイプ(固定・変動)や返済プランなどにより条件が異なるため、契約内容をよく確認しましょう。
•不足分の補填
売却価格がローン残債を下回る場合、いわゆるオーバーローンの状態になると、不足分を自己資金で補填しなければ決済が成立しません。もし手元資金が足りないなら、住み替えローンなどを利用するか、売却を先送りする選択肢も考慮が必要です。
•返済スケジュール
決済日当日に、買主から受け取った売却代金でローン残債を返済し、同時に抵当権抹消の手続きを行う流れが一般的です。銀行のローン窓口をはしごする必要がある場合は時間がかかるため、決済当日は余裕を持って動けるようスケジュールを組みましょう。
2.抵当権抹消費用
•手続きの概要
住宅ローンを完済すると、銀行の抵当権を抹消しなければ物件を売却できません。抵当権とは、ローンを借りる際に設定される担保権で、完済後は解除が可能ですが、自動的に消えるわけではない点に注意が必要です。
•費用の内訳
一般的には登録免許税と司法書士報酬が発生します。登録免許税は1つの抵当権につき1,000円程度(土地・建物それぞれ)かかる場合が多く、司法書士への報酬は1〜2万円前後が相場とされています。ただし、事務所や地域によって料金体系が異なることもあるため、見積もりを比較するのが理想です。
•手続きの流れ
売却決済日に合わせ、司法書士が同席して抵当権抹消登記を行うケースが一般的です。万一、手続きが遅れてしまうと決済や引き渡しの日程をずらさざるを得なくなり、売主・買主ともに予定が狂ってしまうでしょう。
•事例:ローン完済後に手続きが遅れたケース
たとえば、「実は数年前に完済していたが、抵当権の抹消を失念していた」というケースも散見されます。いざ売却の段階になってから慌てて手続きを開始すると、書類を再発行する時間や司法書士のスケジュールが合わず、引き渡し予定日を延期するハメになることがあるのです。このようなトラブルを防ぐためにも、完済時点で早めに抵当権を抹消するか、売却計画が持ち上がった段階でスムーズに進められるよう書類を揃えておくのが望ましいといえます。
ローン返済・抵当権抹消ともに、売却益でカバーできるのか、どのくらいの手数料が上乗せになるのかを事前に把握しておくことが肝要です。もし売却価格がローン残債を大きく下回る見込みなら、追加で数百万円以上を用意しなければならない場合もあり、資金計画や売却タイミングの見直しが不可避となります。こうした問題を避けるためには、不動産会社だけでなく、借入先の金融機関や司法書士とも相談しながら、円滑なスケジュールを組むよう心がけましょう。
不用品処分や引越し費用
不動産売却を機に住居を移す場合、不用品の処分や引越しそのものにもコストがかかり
ます。物件自体の売買だけに意識が向いていると、引越し関連の支出を軽視してしまい、後から「引越し費用が思ったよりも高かった」と予算が崩れるケースが少なくありません。特に長年住み続けていた家からの引越しであれば、荷物量が多い分だけ処分費用や運送費用も膨らむ傾向にあります。
1.不用品処分費用
•粗大ごみの処分
家具や家電などを粗大ごみとして自治体に回収してもらう場合は、数百円から数千円の処分券を購入し、指定日・指定場所に出す必要があります。自治体によって収集ルールや料金体系が異なるため、事前に確認しましょう。引越しシーズン(3〜4月)には予約枠が埋まりやすいことも踏まえて、早めの手配が望ましいです。
•リサイクル業者・買取業者の利用
まだ使える家具や家電をリサイクル業者に引き取ってもらうことで、処分費用を抑えられたり、わずかながら買い取り金を得られる場合もあります。ただし、状態や需要次第では引き取り不可となる場合があるため、複数業者に問い合わせてみると良いでしょう。
•業者一括処分
まとめて不用品を処分したい場合、不用品回収業者に依頼する方法もあります。ただし、市区町村の許可を取得していない「違法業者」も存在するため、トラブル防止のため口コミや実績を調べ、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
2.引越し費用
•時期による変動
引越し費用は、繁忙期(3〜4月)と閑散期(夏・冬のオフシーズンなど)で大きく異なります。同じ荷物量でも3〜4月の料金が閑散期の2倍以上になることも珍しくありません。もし売却・引越しのタイミングを調整できるなら、閑散期を狙うことで大幅なコストダウンが期待できます。
•複数社の見積もり
引越し業者の料金設定は「荷物の量」「搬出・搬入先の距離」「作業人数」「時期」などの要素で決まります。1社だけに相談すると割高なプランを提示される可能性もあるため、複数社から見積もりを取得して比較検討すると良いでしょう。ネット上で一括見積もりサービスを利用すれば手間を抑えながら相場を把握できます。
•荷物の多さに応じた対策
大量の家具・家電を運ぶとトラックの台数や作業員数が増え、費用も嵩んでしまいます。不要なものは早めに処分して荷物をコンパクトにまとめることで、引越し見積もりが安くなる場合が多いです。また、大型の家具を置かずにすむ物件に住み替えるなら、売却前に思い切って整理してしまったほうが後々の負担を軽減できるでしょう。
アドバイス: 「不用品の処分」「引越しにかかる費用」は、物件の売却価格には影響しませんが、最終的な手取りや新居への初期費用に関わる大事なポイントです。売却のタイミングと引越し時期がタイトに重なると、業者手配や荷物整理に追われて精神的にも負担が大きくなることがあります。なるべく早い段階から荷物の整理・処分を始め、引越し業者の見積もりを取るなどの準備を進めておくと安心です。
•チェックリスト例:
1. 不用品をリストアップし、粗大ごみ・リサイクル・回収業者への依頼に振り分ける
2. 引越し希望日を決め、複数の業者に見積もりを取る
3. 荷物のボリュームによっては段ボールや作業人数の追加料金が発生するので要注意
4. 引越し日が繁忙期なら早めに予約し、費用アップを最小限に抑える工夫をする
こうした段取りを踏んでおけば、売却と引越しを同時進行しても余裕をもって対応できるはずです。逆に、計画性がないと引越し費用が倍増したり、処分したい物が売却日までに片付かず家の引き渡しが遅れるなど、思わぬトラブルに見舞われる可能性もあるでしょう。
節税・費用軽減のヒント
ここまでご紹介してきたように、不動産売却には仲介手数料や譲渡所得税、引越し費用など数多くの出費が伴います。しかし、一連のコストをただ受け入れるのではなく、節税制度や不動産会社との交渉などを活用すれば、思ったよりも出費を抑えられる可能性があります。ここでは、「3000万円特別控除」をはじめとする減税制度や、不動産会社へ費用面で折衝を試みる方法などを詳しく解説します。購入・売却のタイミングや交渉テクニック次第で、数十万円単位の節約につながることも珍しくありません。
一方で、控除や特例には厳密な要件が定められているため、きちんと条件を満たしていないと適用外になるリスクがあります。また、不動産会社への値下げ交渉のし過ぎは営業担当のモチベーションに影響し、かえって売却期間の長期化や価格面での不利に結びつくこともあるでしょう。いずれの場合も、「どの制度や手段が自分に合っているか」を冷静に判断し、売却計画を立てる段階で早めに準備することが大切です。
3000万円特別控除などの特例
不動産を売却した際に大きな税金負担を軽減できる制度として、特に有名なのが3000万円特別控除です。これは自宅(居住用財産)を売却した場合に、売却益(譲渡所得)から最大3000万円までを差し引ける制度であり、上手に活用すれば譲渡所得税がゼロになる可能性もあります。ここでは、この3000万円特別控除を含め、代表的な節税制度や長期譲渡所得の特別控除などのポイントをまとめます。
1.3000万円特別控除
•概要: 自宅として使用していた不動産を売却し、譲渡所得が発生した場合、最大3000万円までを控除できる制度です。
•適用要件:
1. 被売却物件が居住用(マイホーム)であること。
2. 居住期間の長さには特別な制限はないが、転居後3年以内の売却などいくつかの時限要件が存在。
3. 配偶者や直系親族への売却ではない。
4. ほかにも細かい条件があるため、国税庁の公式サイトや税理士への確認を推奨。
•申告方法: 翌年の確定申告で譲渡所得を計算し、3000万円まで控除を適用する。もし譲渡所得が3000万円未満なら、理論上は課税所得がゼロになるケースもあるでしょう。
•注意点: ほかの特例(買い替え特例など)との重複が制限される場合があります。売却前に「自分のケースでどの特例が一番有利か」を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
2.長期譲渡所得の特別控除
•概要: 所有期間が5年超の不動産を売却した場合、課税率が低くなる点に加え、特定の要件を満たせばさらなる特別控除が認められるケースがあります。
•適用要件: 基本的には居住用の自宅を長期間保有していた場合など。3000万円特別控除との併用ができない場合もあるため、選択を間違えないよう慎重に確認しましょう。
•ポイント: とにかく売却時の所有期間(売却した年の1月1日時点で5年を超えているか)が大きな分岐となります。1ヶ月違いで所有期間が変わり、税率が約2倍違うケースもあるので、売却時期の設定が極めて重要です。
3.ほかの主要特例
•買い替え特例(課税の繰り延べ): 住み替えを目的に自宅を売却し、一定期間内に新しい居住用物件を購入すると譲渡所得税が繰り延べられる制度。ただし、一時的に課税を先送りにする仕組みなので、最終的には譲渡所得税が発生する場合も。
•相続時精算課税制度の併用: 親子間の贈与や相続時に活用できる制度だが、不動産売却との組み合わせは要件が複雑なため、専門家への相談が必須。
ポイント: これらの特例を活用するには、売却前から「適用要件を満たすか」を確認することが不可欠です。売買契約を締結した後で気づいても条件をクリアできないケースが多いため、「物件を売りに出す前」に税理士などの専門家と打ち合わせるのが理想的です。あわせて、売却のタイミングを少し調整すれば所有期間の判定で有利になるなど、計画的に行えば節税額が数十万円~数百万円になる可能性もあります。
不動産会社への交渉テクニック
仲介手数料などの費用は法律で上限が定められているものの、実際には不動産会社によって報酬体系やサービス内容が微妙に異なります。場合によっては値下げ交渉や広告費の一部負担交渉が可能なところもあり、結果として数十万円単位の節約につながることもあります。ここでは、不動産会社と上手に交渉して費用を軽減するためのポイントと、交渉しすぎるリスクを解説します。
1.複数社への査定依頼で比較検討
•事例: Aさんが自宅売却のために5社から査定を取り、仲介手数料の割引提案や広告費無料キャンペーンを比較したところ、最安の不動産会社と契約した結果、数十万円単位で安く抑えられた。
•メリット: 価格査定の比較はもちろん、手数料やサービス内容(写真撮影、ホームステージングなど)も比較検討できるため、費用対効果が見極めやすい。
•注意点: あまりに安い手数料を要求すると、不動産会社が積極的な広告や営業を避けるケースも考えられる。仲介業者の利益がほとんど出ない状態では、売却活動の優先順位が下がる可能性がある点に留意すべきです。
2.仲介手数料の値下げ交渉
•法律上の上限: (売却価格×3%+6万円)+消費税が仲介手数料の上限とされている。これを下回る設定も認められるが、上限を超えるのは違法。
•交渉の仕方: 「ほかの不動産会社ではもう少し安い手数料を提示してくれた」「手数料を少しでも抑えたいが、その分紹介で買主を探してほしい」など、業者にとっても利点がある条件(追加の買主紹介、物件の紹介など)を提示すると、前向きな話し合いにつながることがある。
•デメリット: 値下げ交渉を強く要求すると、仲介業者との関係が悪化し、売却活動に悪影響が出る可能性がある。営業担当のモチベーションを下げすぎないよう、節度ある交渉を心がけるのがコツ。
3.広告費やサービス内容の交渉
•広告費の取り扱い: 一般的に、不動産会社が自社負担で広告やポータルサイトへの掲載を行ってくれる場合が多いが、地域によっては別途広告費用を請求することもある。そこで、広告費の一部負担を見直してもらうよう交渉する手も。
•付加サービスの有無: 写真撮影やホームステージング、オープンハウスの実施などのサービスを「手数料の範囲内」で提供してもらえるのか、追加費用を取られるのかは業者によって異なる。サービス内容を詳しく聞き取り、必要ないサービスを断ることでコストダウンになる場合もある。
4.交渉しすぎによる悪影響
•売却活動が後回しに: 中には、極端な値下げ要求で不動産会社が「そこまでコストをかける余地がない」と判断し、ほかの物件を優先するケースもある。結果として、売却期間が長引き相場が下落したり、買主がつきにくくなったりする恐れが出てくる。
•担当者との信頼関係: 不動産の売買は、高額かつ信頼関係が不可欠な取引です。仲介手数料をめぐるトラブルやギクシャクしたやり取りは、担当者の提案力や交渉力を引き出せない原因にもなるでしょう。
◯あわせて読みたい記事
住宅ローンが残っていても住み替えは可能?成功のためのポイント
まとめ
本記事では、仲介手数料や印紙税、譲渡所得税などの主要な費用項目に加え、ローン残債の清算や抵当権抹消、引越しに伴う追加費用などを網羅的に解説しました。さらに、3000万円特別控除などの節税制度や、不動産会社との交渉テクニックも紹介し、費用を少しでも抑えるためのポイントを提示しています。読者の皆さまには「費用をしっかり把握し、損失を最小限に抑える」「疑問があれば専門家に相談する」という姿勢を持っていただきたいと思います。
費用把握で損失を最小限に抑えよう
不動産売却を成功させるには、事前の費用計算が欠かせません。複数社への査定依頼やローン残債シミュレーション、減税制度の確認など、早めに動くほど余裕をもって対策できるはずです。たとえば「確定申告の手順を調べる」「引越し費用を減らすために不用品を事前処分する」「仲介手数料の再交渉を検討する」など、今日から始められるアクションは多彩にあります。適切な対策を取れば、何十万円単位の費用削減が可能になることもあるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、賢くコストを抑えて、不動産売却をスムーズに進めてください。
◯あわせて読みたい記事