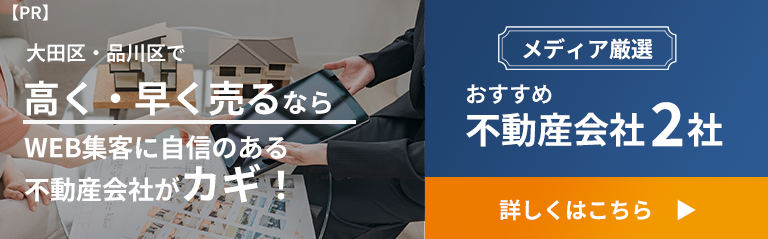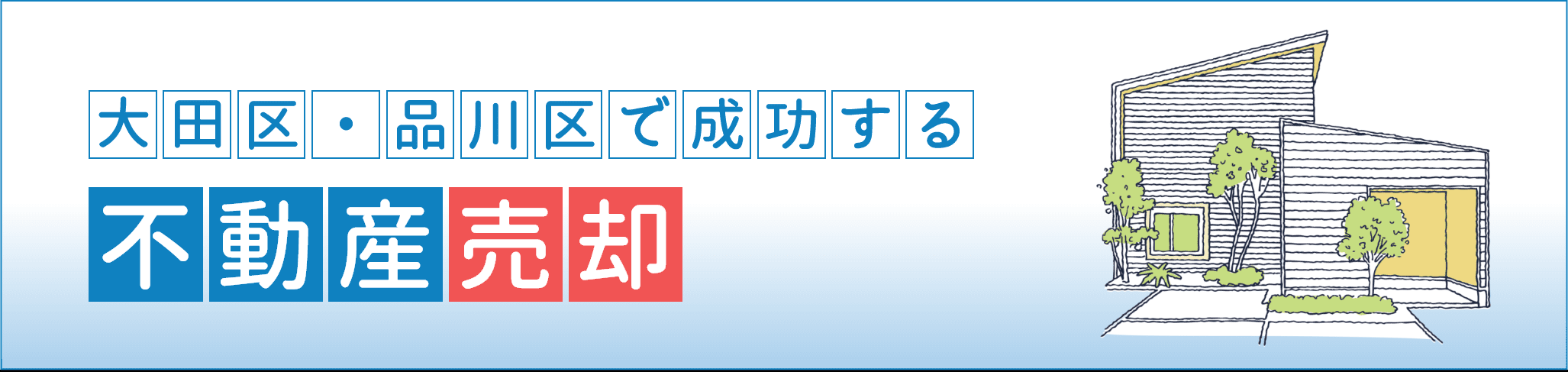不動産売却後のトラブルを防ぐアフターフォロー体制の整え方
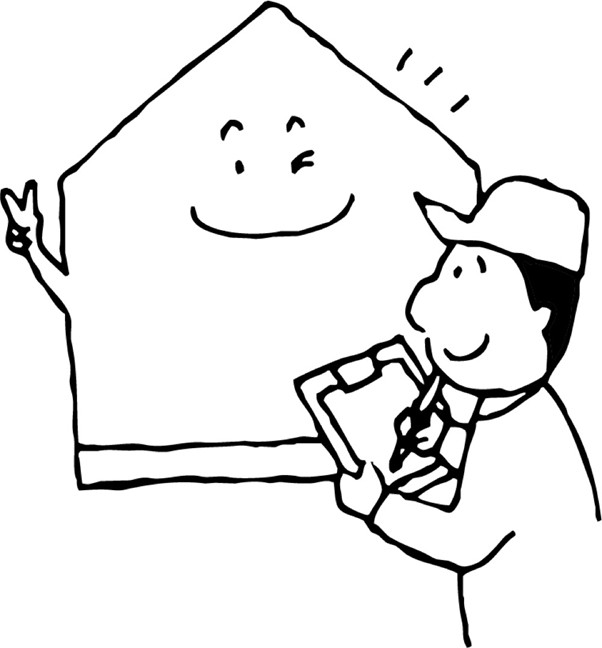
不動産を売却する際、多くの方は「引き渡しが終われば、あとはもう大丈夫だろう」と思いがちです。しかし、実際には売却後にもさまざまなトラブルが起こる可能性があるのが不動産取引の現実です。
例えば、物件の隠れた不具合や書類不備、さらには買主が発見した設備トラブルなど、多彩なリスクが潜んでいます。こうした問題が発生すると、契約後であっても売り主に契約不適合責任を問われる場合があり、最悪の場合は契約解除や損害賠償に発展しかねません。
そこで近年注目されているのが、売却後のアフターフォロー体制を整えておくことの重要性です。売り主自身や媒介を担当する不動産会社が、引き渡し後も一定のサポートや保証、窓口機能を提供することで、万一のトラブルを早期に解消し、買主・売り主双方が安心して取引を終えられます。
売却完了というゴールを迎えても、実はそこからが本当のスタートと言っても過言ではありません。アフターフォローがしっかりしているかどうかで、売り主の負担も買主の満足度も大きく左右されるのです。
ぜひ本記事を参考に、安心かつスムーズな不動産売却を目指してみてください。
目次
引き渡し後の問題例

不動産売却が無事に完了し、引き渡しも済んだからといって、すべてが終わるわけではありません。実際には、買主が物件に住み始めてから「こんな問題があるとは思わなかった」と気づき、売り主にクレームを出してくるケースが珍しくないのです。
ここでは、「契約後のクレーム対応」と「設備不具合・書類不足」という二つの角度から、具体的な事例や注意点を考察していきます。
契約後のクレーム対応

1. 契約後のクレーム発生リスクとは
不動産売買契約では、売り主と買主が合意して決済と引き渡しが完了すれば取引自体は成立しますが、その後に見つかった問題をめぐってトラブルが起きることもあります。特に以下のようなシナリオが典型例です。
•物件の隠れた欠陥
引き渡し前の内覧やホームインスペクションでも発見できなかった雨漏りや基礎の亀裂などが、買主が入居後に判明する。売り主がその欠陥を事前に把握していた場合、告知義務違反や契約不適合責任を問われる恐れがあります。
•近隣トラブルの潜在化
隣地や管理組合との争い、騒音や越境といった問題を売り主が黙っていたケースもクレームの原因になりやすいです。買主は引っ越してすぐに近所から苦情を言われ、「売り主に騙された」と感じるかもしれません。
このように契約後のクレームは、売り主にとって大きな精神的・金銭的負担となるだけでなく、売り主と買主の関係を深刻に悪化させるリスクが高いです。
2. 具体的なクレーム事例
1).事例A:雨漏りの再発

•一度修理したと説明していた雨漏りが、買主が住み始めてから再発。買主が「まったく修理されていない」と主張し、修理費用の全額負担を売り主に求める。
•実際には修理はされていたが、根本原因が解消されていなかったケースなども多く、結局は売り主と買主で再度話し合いを行う羽目になり、時間と労力を浪費する。
2).事例B:境界問題によるクレーム
•土地の売買で境界が不確定だったにもかかわらず、売り主が「問題ない」と説明。後日、買主が立ち会い測量をしたところ隣地との越境が判明し、塀の移動などが必要になった。
•買主は「こんなに大きな工事が必要だとは聞いていない」と激怒し、契約解除や賠償請求を検討する事態に。売り主は測量費や工事費の一部負担を余儀なくされる。
3.事例C:周辺騒音と管理規約の不備

•マンション売却後、買主が夜間の騒音に悩んで管理組合に相談するも、管理規約が形骸化しており対応が進まない。実はこの問題は売り主も把握していたのに告知していなかった。
•買主は「売り主が知っていたはずなのに隠していた」と不信感を募らせ、損害賠償の交渉に発展。長期の争いに巻き込まれることに。
3). クレーム初動対応の重要性
買主がクレームを申し立ててきた場合、売り主がどれだけ迅速かつ誠実に対応できるかで、問題の長期化を防げるかどうかが決まります。
アフターフォロー体制が整っていれば、適切な窓口があり、売り主や不動産会社の担当者が速やかに事態を把握し、解決策を示すことが可能です。
•連絡体制の明確化: 買主が困ったときに連絡すべき担当者や電話番号、メールアドレスを明示しておき、常に対応できるようにしておく。
•弁護士や専門家との連携: トラブルが複雑化しそうな場合、あらかじめ売り主が弁護士など専門家と連携できる体制を用意しておくと安心。
•保険や保証制度: 中古住宅瑕疵保険など、保険を活用することで修理費や賠償金をカバーできる場合がある。契約前に保険加入しておけば、万一のクレーム時にも負担が減る。
設備不具合・書類不足

契約後のクレームの中でも、設備不具合や必要書類の不足が原因で買主が不満を抱くケースは多いです。これらは見落とされがちですが、実際に生活を始めてみると買主に直接的な不便が発生しやすい部分でもあります。
1. 設備不具合の典型例
1).給湯器・エアコンの故障

•内覧時には動作していたが、いざ入居して使おうとしたら故障していたというパターン。中古物件では発生しやすく、売り主が「動作確認して問題なかった」と主張しても買主が納得しないことがある。
•特に給湯器やガスコンロなどは寿命が迫っている場合があり、売り主が注意点を事前に説明するか、価格交渉に盛り込むかしていれば揉めにくい。
2).水回りの漏水・配管トラブル

•シンク下や洗面台、浴室などで水漏れが起こると、カビや腐食の問題に発展する恐れがある。売り主が以前に修理した履歴や原因を詳細に伝えていないと、買主は「知らされていなかった」と不満を感じる。
•事前に配管調査や簡易インスペクションを行い、結果を開示することで信頼を得やすくなる。
3).不具合の発見時期による揉め事
•引き渡し直後に不具合が発覚した場合、買主は「最初から壊れていたのではないか」と疑うが、売り主は「たまたま運悪く壊れた」と主張するなど、意見が対立しやすい。
•アフターフォロー体制がないと、こうした状況でスムーズに話が進まず、深刻化することがある。
2. 書類不足が招く混乱
1).修繕履歴や重要事項説明の不備

•物件の修繕履歴が曖昧で、どのタイミングでどんな工事をしたのか分からないと、買主が「修理したというが本当か?」と疑心暗鬼になる。また、重要事項説明書に記載すべき情報が抜け落ちていると、契約後に見つかった際に売り主の義務違反が問われることがある。
•稀に、リフォーム済みを謳いながら実際には粗雑な工事しかしていないケースもあり、後々の検査で判明すると大きなトラブルに。
2).住宅ローンの審査書類不足
•買主がローンを組む際、登記簿や測量図、建築確認済証などが必要になる。売り主側の書類管理が不十分だと、買主がスムーズに審査を受けられず、契約破談に至ることも。
•特に、土地の境界確定書や公図が存在しない場合、金融機関から「境界不明瞭な土地は担保評価が低い」と見なされるリスクが高い。
3).保証書や取扱説明書の紛失
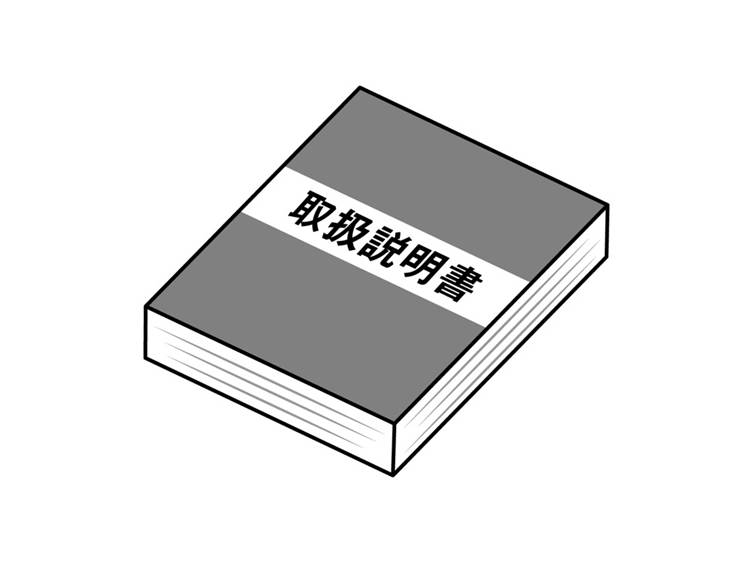
•エアコンや給湯器、IHクッキングヒーターなどの設備に保証書が付いている場合、売り主が保管していないと買主が故障時に無料修理を受けられず不満を募らせる。
•もし保証書を紛失したなら、その設備の購入・設置業者の連絡先や、おおよその購入時期を伝えておくなど、買主がトラブル発生時に対処できる術を提供すると良い。
3. 売却後に責任を問われる可能性
契約後に発覚した問題であっても、「売り主が知っていたか」「知っていて告知を怠ったか」が論点となり、売り主の契約不適合責任が追及される場合があります。
程度によっては契約解除や損害賠償につながりかねないため、下記の対策が求められます。
•引き渡し前の詳細インスペクション
できるだけ専門家による建物検査(ホームインスペクション)を実施し、結果を買主に提示することで紛争を防ぎやすいです。
•告知書や設備表への正確記載
設備が故障しやすいかどうか、修理や交換歴があるか、動作確認した日付などを明示。万が一のとき、売り主が「一定の情報は事前に伝えていた」と立証しやすくなる。
引き渡し後の問題例まとめ
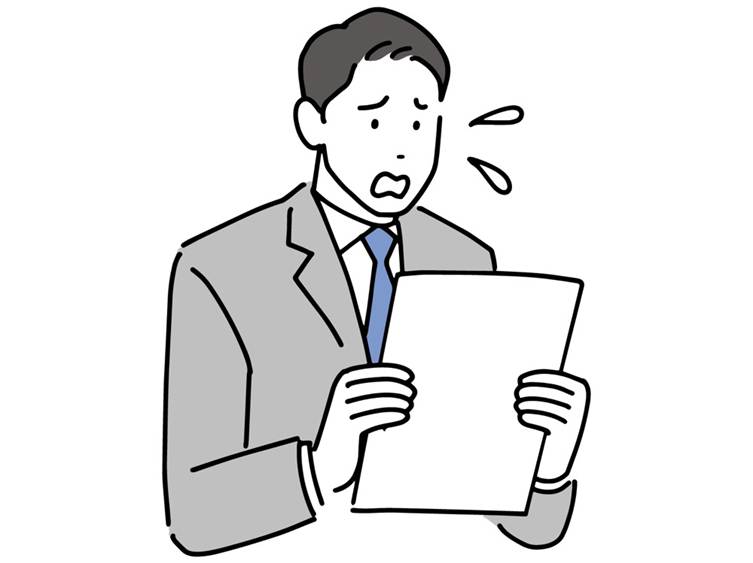
•契約後のクレーム対応
•雨漏りや越境など、物件の本質的なトラブルが後から見つかると、買主から契約解除や損害賠償を求められるリスクが高い。
•迅速かつ誠実に対応できるアフターフォロー体制があるかが、問題の長期化を防ぐカギとなる。
•設備不具合・書類不足
•給湯器や水回りなどの設備が引き渡し後に故障していた場合、売り主がどこまで責任を負うかで対立が生じやすい。
•書類(修繕履歴、重要事項説明書など)が不十分だと、買主のローン審査や契約手続きで混乱が起き、契約破談になることも。
•売り主の責任

•「知らなかった」では済まされないケースが多々あり、契約不適合責任を免れない場合もある。事前の情報整理や適切な告知が不可欠。
不動産売却は引き渡しが完了すれば終わりではなく、その後にも設備不具合や境界問題、隣人トラブルなどが表面化し、買主からクレームを受ける可能性があります。雨漏りや給湯器の故障、書類不足といった問題は、売り主にとって契約不適合責任を問われかねないリスクです。
特に設備不良や修繕履歴の不備を知りながら告知していなかったり、境界が曖昧な土地を「問題なし」と説明していた場合は、売り主が補償負担を余儀なくされるケースもあります。
こうしたトラブルを防ぐには、引き渡し前にしっかりとインスペクションを行い、必要な情報を買主に明示することが大切です。また、引き渡し後も買主が困ったときにすぐ連絡できるアフターフォロー体制を整えておけば、問題が大きくなる前に手を打てます。
◯あわせて読みたい記事
不動産売却の手続きとは?必要書類の種類・取得方法・特例を紹介
アフターフォロー策

不動産売却のプロセスは、決済と引き渡しが完了したら終わりと思われがちですが、実際には売却後にもトラブルや問い合わせが発生する可能性があります。
契約不適合責任の問題や隠れた瑕疵(かし)の発覚などが起きた場合、売り主が買主とのやり取りに対応しなければならない場面が出てくることは珍しくありません。
そこで重要なのが、アフターフォローの体制を整えておくことです。本章では、「連絡先共有・保証制度」と「不動産会社選びでフォロー確保」という二つの視点から、売り主が取れる具体的なアフターフォロー策を解説します。
連絡先共有・保証制度

1. 連絡先を明確にしておく
1).クレーム・問い合わせの窓口
•引き渡し後、買主が「設備の調子がおかしい」「契約時の説明と違う点がある」などを発見した場合、まず誰に連絡すべきかを明確にしておくのが大切です。売り主が直接対応するのか、不動産会社の担当者が窓口になるのかを事前に決めておくと、トラブルがこじれにくくなります。
•もし売り主自身が対応可能な場合は電話番号やメールアドレスを伝え、不在が多い場合は不動産会社や管理会社が一次対応してくれる体制を整えるとスムーズです。問い合わせが来た際に「どこに連絡すればいいの?」と買主が迷わずに済むよう、書面や引き渡し時の口頭で説明しましょう。
2).緊急時の連絡手段
•水漏れなどの突発的なトラブルが発生した場合、迅速な対処が求められるため、夜間や休日でも連絡可能な緊急ダイヤルを設置している不動産会社や管理会社があると安心です。
•個人の売り主では24時間体制で対応するのが難しいため、有料のサポートサービスや不動産会社との追加契約でカバーすると良いでしょう。
3).トラブル対応マニュアルの作成

•可能であれば、物件の設備取扱説明書や問い合わせ先などをまとめた簡易マニュアルを用意し、買主に渡すとさらに親切です。
たとえば「エアコンは○年製で、故障時の修理は○○電気が対応」「給湯器のメーカーと保証についてはこの連絡先へ」など、一覧にしておけば買主がスムーズに動けます。
•売り主としても「買主に確実に必要情報を伝えた」という形が残るため、後で「聞いていない」と争われるリスクを減らせます。
2. 保証制度の活用
1).中古住宅瑕疵保険・瑕疵保証制度

•中古住宅を売る際に加入できる瑕疵(かし)保険があります。これは物件の基礎や屋根・外壁など主要構造部分に欠陥が見つかった場合に、保険金で修理費用をまかなうことができる仕組みです。
売り主が加入しておくと、引き渡し後に重大な欠陥が判明しても、保険金で対応できるため買主が安心しやすく、売却時のアピールにもなるでしょう。
•瑕疵保険に加入するには、保険会社が指定する検査機関で建物検査を受け、一定の基準を満たす必要があるため、時間と費用がかかることがありますが、売却期間が長期化しにくくなるメリットがあります。
2).設備保証・機器保証

•給湯器やエアコンなど、住み始める際に動作不良を起こしやすい設備については、短期の保証制度を利用できるケースがあります。たとえば、「売り主負担で3か月保証を付ける」といった形です。
•こうした保証を付けることで、買主は「もし故障しても一定期間内は安心」と考えられ、売り主への不信感を防げます。結果的に値下げ交渉を緩和し、早期成約につながることが期待できます。
3).保険加入のメリットと費用対効果
•瑕疵保険や設備保証にはコストがかかるものの、その保険料以上に“買主の安心感”を生み、売却価格を維持できる可能性が高まるというメリットがあります。
•売り主としては、保険料を負担する代わりに高めの売却価格を提示できるかどうかを検討し、トータルの収支を計算してみるといいでしょう。特に不具合の疑いがある築古物件では、保険を付けるメリットが大きい場合があります。
不動産会社選びでフォロー確保

アフターフォローを万全に整えるには、売り主一人で対応する限界があるのも事実です。そこで頼りになるのが、不動産会社のサポート体制や仲介担当者の力量です。物件の契約手続きや決済完了後にも、どのようなフォローを提供してくれるかは、不動産会社ごとに大きく異なります。
1. 売却後も手厚いサポートを提供する会社の特徴
1).アフターサービス明記
•大手不動産会社やサービス志向の強い仲介会社は、売り主・買主へのアフターフォローを「プラン」として明示していることがあります。たとえば「引き渡し後○か月以内の設備トラブルは仲介会社が無償相談に応じる」といった内容が契約書に盛り込まれるケースです。
•会社のウェブサイトやパンフレットで「売却後もサポート」などと謳っているか確認し、細かな条件を面談時に質問するのが望ましいです。
2).契約不適合責任への対応協力

•万一トラブルが起きたときに、仲介した不動産会社が間に入り、買主と売り主の双方の意見を調整してくれるかどうかは非常に重要です。
•担当者が「契約後はタッチしません」などと発言する企業もあるため、事前に「契約後に問題が発生したら、どんなフォローをしていただけますか?」と確認しておくと安心です。
3).定期的なフォロー連絡
•一部の会社や担当者は、決済後も定期的に「お困りのことはないですか?」と連絡してくれることがあります。こうしたコミュニケーションがあると、売り主だけでなく買主も安心しやすいですし、潜在的なトラブルを早期発見しやすいです。
2. 担当者との信頼関係
1).担当者の対応姿勢を見る

•不動産会社のポリシーだけでなく、実際に対応する担当者がどれだけ親身に動いてくれるかが成功のカギを握ります。契約前の相談段階で、自分や買主の疑問や要望にどの程度応じてくれるのかを観察すると良いでしょう。
•担当者が「売り主と買主の橋渡しを丁寧に行う」という意識を強く持っていれば、引き渡し後にも適切な対処やアドバイスを期待できます。
2).交渉力と調整力
•アフターフォローでも、設備不具合や費用負担を巡って買主と売り主の主張が対立することがあります。そのときに担当者が交渉役となり、双方が納得する落とし所を見つけられるかが重要です。
•曖昧な表現で逃げる担当者より、プロとしての知識や経験を活かして具体的な解決策を提示できる人を選ぶと安心です。
3).媒介契約前の確認項目
•一般媒介・専任媒介などの契約形態を結ぶ前に、「契約後にトラブルが起きたらどうサポートしてもらえますか?」と具体的に質問し、回答を文書化しておくと良いです。
•「アフターフォローは法的に義務がない」としても、会社の方針や担当者の努力次第で対応が大きく変わるため、面談時にしっかり比較検討しましょう。
アフターフォロー策まとめ

1.連絡先共有・保証制度
•売却後のトラブルを円滑に処理するには、買主が困ったときにどこへ連絡すればよいのかを明確にし、設備や構造に対する保証制度を取り入れるのが効果的。
•瑕疵保険や設備保証を付けるとコストはかかるが、買主の安心を高め、値下げ交渉の圧力を和らげるメリットもある。
2.不動産会社選びでフォロー確保
•売却後もサポートしてくれる不動産会社や担当者を選べば、万一のトラブル時に調整役として動いてもらえる。
•事前にアフターサービスの有無や内容を確認し、契約不適合責任への対応方針や連絡体制をチェックすると安心。
売り主がどれだけアフターフォロー体制を整えておくかで、引き渡し後に起こり得るトラブルの長期化や損失を最小限に抑えることができます。次章のまとめでは、売却完了後にもしっかりとしたサポートを念頭に置くことで買主の信頼を得る方法を、改めて振り返ります。
◯あわせて読みたい記事
まとめ:売却完了後も万全なサポートを念頭に

不動産売却は、引き渡しが終わればすべて完了というわけではなく、その後もさまざまなトラブルが起こりうるのが実情です。
契約直後に気づかれなかった設備不具合や境界問題、書類の不足による手続き上の混乱など、買主の側に不安や不満が生じた場合、売り主は契約不適合責任を問われる恐れがあります。
このとき重要なのがアフターフォロー体制です。引き渡し後の問い合わせ窓口を明確にする、瑕疵保険や設備保証などを活用して万が一の修理費用を補えるようにしておくなど、売り主があらかじめ仕組みを整えていれば、問題が大きくなる前に解決へと導きやすくなります。
また、フォローの手厚い不動産会社を選べば、担当者がトラブルの仲介役となり、円満な話し合いをサポートしてくれます。こうした体制があれば、買主も安心して契約に踏み切りやすく、結果的に売却価格や成約率にもプラスに働きます。
売却完了後も「万全なサポートを念頭に」置いておくことで、買主との信頼関係を維持し、スムーズかつ満足度の高い取引を実現できるでしょう。
◯あわせて読みたい記事