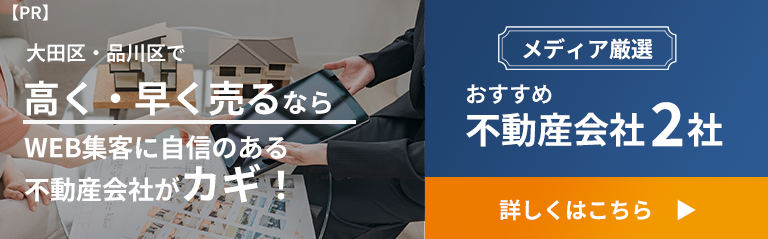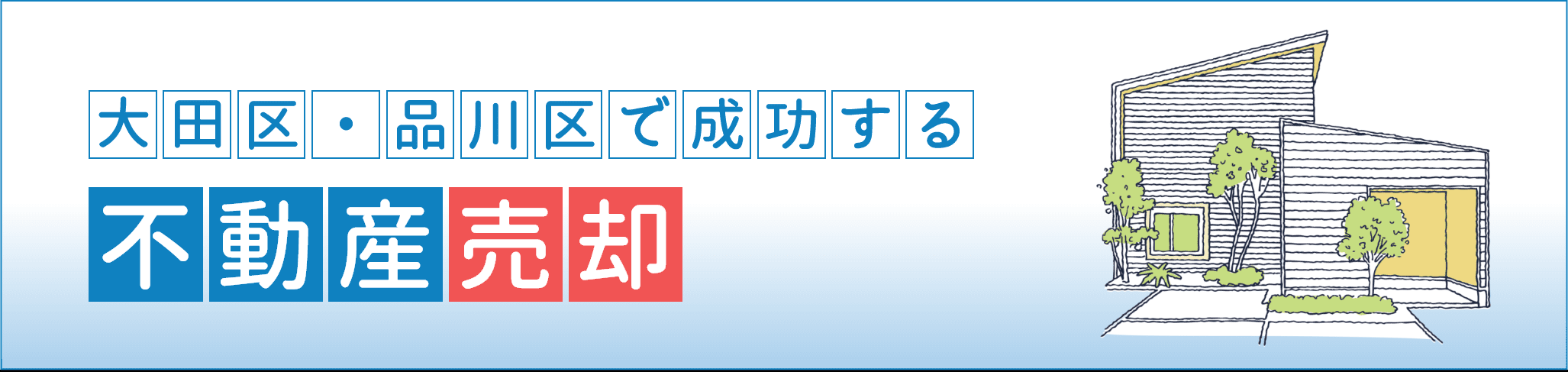不動産売却前に行う境界確定測量の重要性と手続き

不動産を売却しようと考えている方のなかには、敷地境界が不明確だったり、古い杭や塀が本当に正しい境界なのか確信が持てずに悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
実は、境界が曖昧なままで売りに出すと、後から「越境していた」「図面と実際の面積が違う」などのトラブルが発覚し、買主が不信感を抱いて取引を中止したり、売却価格を大幅に下げざるを得なくなったりするリスクがあります。
そこで活用したいのが、境界確定測量です。測量士や土地家屋調査士が隣地との境界を客観的なデータに基づいて明確化し、必要に応じて隣地所有者との立会いを行いながら合意形成を図ります。
こうして「正式な境界」をはっきりさせれば、買主は安心して購入を検討でき、ローン審査においても担保評価の低下を防げる可能性が高まるのです。
本記事では、境界確定測量とは具体的にどのような作業なのか、どんな流れで進めるべきなのか、そして費用や時間がかかってもやる意義がどこにあるのかをわかりやすく解説します。
特に売却を間近に控えている方は、「境界がはっきりしていない」というだけで数百万単位の損を被るリスクも否めません。逆に、しっかりと測量しておけば、後々のトラブルや値下げ交渉を回避し、円滑な売却活動を進められるでしょう。
ぜひ本記事を参考に、測量の重要性と手続きのポイントを学び、不動産売却に万全の準備を整えてください。
目次
境界確定測量とは

不動産を売却する際、物件そのものの状態や周辺環境が注目されるのはもちろんですが、土地そのものの境界がどれだけ正確に確定しているかも極めて重要な要素です。築年数の古い住宅地や相続で受け継いだ実家などでは、実際にどこからどこまでが自分の敷地なのか、あるいは隣地との共有部分がどこなのかが曖昧になっているケースが少なくありません。
こうした状況を放置したまま売却を進めると、後から越境問題や地積誤差の発覚によって買主が大きな不安を抱き、契約が破談になったり大幅な値下げを要求されたりするリスクが高まります。そこで重要になるのが境界確定測量です。
本節では、まず境界確定測量の狙いやプロセスを「隣地境界明確化」の観点から解説し、さらに「将来トラブル防止」の視点から、測量を行わないまま売却するとどういったリスクがあるのかを事例を交えて考察します。
隣地境界明確化
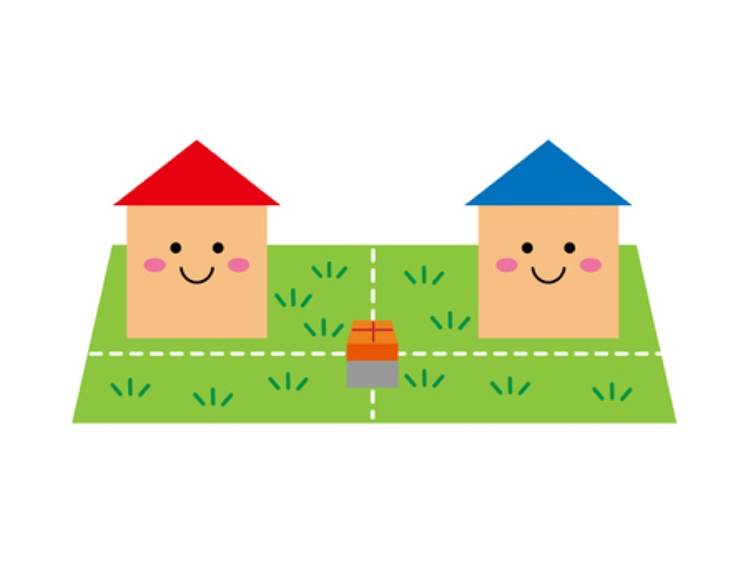
1. 境界確定測量の目的
1) 売却前に境界を明確にする理由
不動産を売却しようとするとき、買主は「自分が取得する敷地の正確な範囲や面積」を知りたいと考えます。なぜなら、そこに建物を建てる、改築する、あるいは駐車スペースにするといった計画がある場合、実際にどれだけのスペースが使えるかを把握していないと将来のプランが立てにくいからです。
また、金融機関が住宅ローンや事業ローンの担保評価を行う際も、境界が曖昧な土地は「法的リスクがある」と判断され、融資額が減らされたり審査が通りにくくなったりする懸念があります。
•契約不適合責任のリスク
境界が不明なまま「だいたいこの辺りが敷地です」と言って売却を行い、引き渡し後に買主が「実は隣地に越境していた」とか「公図面積と実測面積が大きく違う」と発覚すると、契約不適合責任を問われる可能性があります。
買主がローンを組めなくなるケースもあり、売り主が損害賠償などを請求されるリスクも否定できません。
2)境界不明で売却を進めるリスク
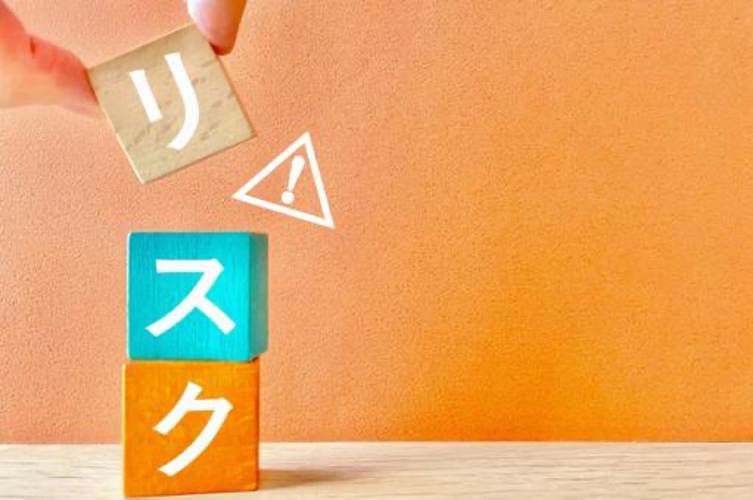
多額の仲介手数料や広告費をかけて物件を市場に出しても、内覧段階で「境界がはっきりしない」と判明すれば、買主が二の足を踏んでしまい、結局売却に至らず時間とコストを浪費する可能性が高まります。
もし売り主がその時点で焦って測量を開始しても、隣地所有者との折衝に時間がかかり、買主が待ちきれずに他の物件へ流れてしまうといった二重苦に陥ることも珍しくありません。
2. 境界点・境界杭の存在
境界確定測量を行う際、真っ先に確認するのが「敷地の四隅に境界杭があるかどうか」です。多くのケースで、何らかの杭やブロック塀、フェンスなどが既に設置されているかもしれません。
しかし、それらが公的に認められた正式な境界とは限らない点が注意を要します。以下では、その理由や測量上の検証プロセスを説明します。
1.杭や塀が誤った位置にある例
時代をさかのぼると、隣同士で「ここが境目だよね」と口頭で取り決めて杭を打ったり、塀を設置したりしていた例がしばしば見受けられます。ところが、その口約束や昔の認識が現在の登記簿や公図上の情報と食い違う場合、正式な境界とは見なされない可能性があるのです。
2.測量士の役割

測量士(または土地家屋調査士)は、古い公図や過去の合意文書、航空写真などを総合的に検証し、どこが正しい境界線なのかを探ります。
杭や塀が現存していても、その位置がどの時点の取り決めを反映しているかを調査し、隣地所有者と売り主の合意を得る形で最新の境界点を再設定します。
•複数回の境界変更
古い住宅地では、数十年の間に何度も建て替えや区画変更が行われており、当初の境界合意が更新されていないケースが多々あります。こうした地域こそ、売却前に測量をしないと大きなリスクを抱えることになるでしょう。
将来トラブル防止

境界が曖昧なまま物件を売りに出してしまうと、たとえ一時的に買付申込みを得られても契約手続きの最終段階でトラブルが表面化することがあります。
特に、越境や地積誤差といった境界関連の問題は高額の費用負担や対立を招く可能性が高く、売り主と買主の信頼関係を一気に損ねかねません。ここでは、具体的なトラブルの例と、境界確定測量がそれをどのように回避できるかを解説します。
1. 越境や共有部分の争い

1) 隣地建物の越境
隣家の建物や塀、植木が自分の敷地に入っている「越境」ケースは思いのほか多く、その逆もしかりです。売り主が認識していなかった越境が、引き渡し後に買主が行ったリフォーム調査などで明らかになると、買主は「もともと知らされていれば買わなかったかもしれない」と主張し、契約不適合責任を追及するか、値下げ要求をする可能性が高まります。
•建物の一部越境
壁や軒先が数センチ越境している場合でも、隣地所有者が協力的でなければ撤去工事が必要となり、数十万円の負担が売り主(あるいは買主)にのしかかる大問題に発展するかもしれません。
2) 共有部分のあいまいさ
隣地との間に共有の通路が存在する場合や、敷地が一部共有名義になっている場合、それを売り主がはっきり把握していないと、買主側が「どこまで使えるのか」と混乱します。境界確定測量を通じて書面化すれば、権利関係を明白にして将来の紛争を避けられます。
2. 境界をはっきりさせるメリット

1) 買主のローン審査が通りやすい
金融機関は、担保となる土地の境界が不明瞭な場合、「どの程度の面積を確実に担保として評価できるか分からない」と判断し、融資額を抑えたり審査自体を保留したりすることがあります。
境界確定測量を経て、合意書や確定図が揃っていれば、金融機関も安心して融資ができ、結果的に買主がローンを組みやすくなるわけです。
2) 売却後のクレーム減少
売り主が「測量済みで、隣地承諾も得ています」と提示できれば、契約不適合責任や追加的な費用負担を問われる場面が大幅に減ります。越境問題や面積のズレが先に解決されているため、買主も「想定外の欠陥が出てくるリスクは低い」と考え、スムーズに契約へ進むことが多いです。
3) 事例やデータ
•境界トラブル放置で数百万円値下げ

築古の一戸建てで、隣地との境界がはっきりしていなかったため、複数の買主候補から敬遠され、最終的に相場より数百万円安く売却せざるを得なくなった例が報告されています。
逆に、先に測量を行って境界を明らかにしていたら、当初の希望価格に近い金額で売れた可能性が高いでしょう。
•測量費用は投資か損失か
境界確定測量に要する費用は数十万円~100万円以上と安くはありません。しかし、測量なしのまま売却して何百万円も値下げするリスクや、買主が見つからず長期間売れ残るリスクと比べれば「先行投資」と考えられる面もあります。
3. 将来トラブルを避けるための心構え

境界不明は、売却直前になって焦って行うのではなく、早めの段階で測量士に相談するのが得策です。特に相続や古い住宅地での所有物件は、公図と現況が異なる確率が高いため、売却スケジュールを組むうえでも測量期間を想定に入れて余裕を持つと失敗しにくいです。
•測量後に広がる可能性
もし隣地所有者が協力的で、境界確定が円滑に行われれば、すぐにでも売り出し価格や仲介業者とのプランを固められます。買主候補が見つかったときにも「測量済みで境界確定書があります」と言えるので、商談がスピーディに進むでしょう。
•地積更正登記も検討

測量の結果、登記簿の面積と実測面積が異なる場合は地積更正登記を合わせて行うのが理想です。公図や法務局の地図が実態に合致する形に更新されるため、買主がローン審査や将来的な売却を行う際にもメリットがあります。
境界確定測量は、一見地味な作業に思えますが、不動産売却の成功可否や売却価格に直結する極めて重要なプロセスです。特に古い住宅地や相続物件などでは、公図上の形と現況が異なる例が少なくなく、そこを放置して売却を進めると越境や共有部分の不明確さが契約トラブルにつながります。

実際、測量を回避したまま売り出して複数の買主候補に敬遠され、値下げや契約破談を余儀なくされるケースも存在します。その一方、測量をきちんと行い、隣地所有者と境界を合意したと示せれば、買主は安心感を持ち、金融機関のローン審査にもプラスに働くため、売り主は適正な価格と短い期間での成約を期待できます。
測量費用自体は数十万~100万円以上かかることもありますが、後々の紛争や値下げ交渉を回避できる可能性を考えれば、投資価値は十分に見込めると言えるでしょう。今後の不動産売却をスムーズに、かつ高評価で成立させたいのであれば、境界確定測量は避けては通れない要件と意識して、早めに行動に移すことをおすすめします。
◯あわせて読みたい記事
手続きの流れ

不動産売却において、境界が曖昧な場合は境界確定測量を行う必要が生じますが、実際にはどのようなステップで手続きを進めるのか、事前に把握しておくことが極めて重要です。敷地境界は単なる「自宅と隣地の境目」という意味合いにとどまらず、法務局の登記情報や買主のローン審査(担保評価)にも大きく影響を及ぼします。
もし境界がはっきりしていないまま売りに出してしまうと、後から「越境だった」「面積が想定より少ない(または多い)」といったトラブルが判明し、売却交渉が長引いたり価格を大幅に下げざるを得なかったりするケースも珍しくありません。

ここでは、まず「測量士依頼・隣地立会い」に焦点を当て、実際に測量を着手して隣地所有者との合意を得るまでの具体的な流れや費用・期間を解説します。続いて、「書類作成・法務局登記」として、測量結果を文書化し公的に反映させるためのステップを見ていきましょう。
これらの作業を理解しておけば、売却プロセスをスムーズに進めるうえでどのような準備が必要か、先読みして行動できるようになります。
測量士依頼・隣地立会い
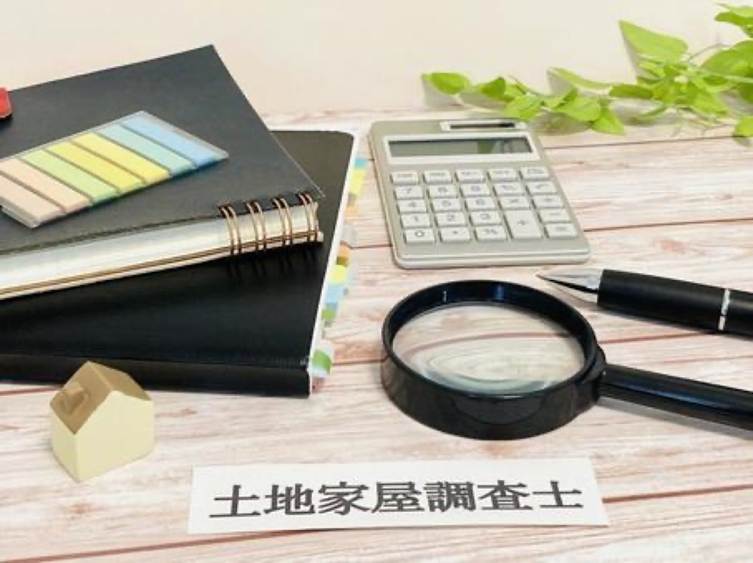
1. 測量士(または土地家屋調査士)に依頼する手順
境界確定測量は、一般的に「土地家屋調査士」あるいは「測量士」が受託して行うものです。大まかな手順は以下のように進められます。
1.概算費用とスケジュール確認
•まずは測量士に相談し、どのくらいの費用が必要になるか、どの程度の期間が想定されるかを把握します。敷地形状が複雑、隣地が多数ある、あるいは市街地の入り組んだエリアなのかなど、さまざまな要因でコストや期間が変動します。
•具体的な見積もりを取る際には、敷地面積や公図との整合性の確認などの初期調査を行い、おおよその作業内容を特定します。
2.周辺の公図や登記情報のチェック

•売り主が保管している公図や登記簿のデータを照合しながら、法務局で最新の公図や地積測量図を取得し、すでに登録されている境界情報を精査します。
•ここで「公図上はきれいな長方形になっているのに、現場では角が削られている」などの相違を把握することで、測量時に重点的に確認すべきポイントが明確になります。
3.隣地所有者への協力要請
•境界を確定するには、自分の敷地だけでなく隣地所有者の立会いと合意が不可欠です。測量日程の調整、事前説明の資料を用意するなど、入念にコミュニケーションを取ります。
•隣地所有者が非協力的だったり、多忙で立ち会いの日時が合わなかったりすると、スケジュールが大幅に伸びることがあります。最悪の場合、調停や裁判など専門家を交えた長期交渉が必要になるケースもあるため、早めの行動が肝心です。
2. 隣地所有者との合意形成

実際の測量当日、測量士は実測機器を用いて境界線を正確に測定します。公共測量や登記資料を参照しながら、隣地との境界部分や道路との接点などを詳細に調べ、隣人と売り主(依頼主)の両者が同席する場で位置を確認していきます。
1.杭の設置や確認作業
•測量の結果に基づき、新しく杭を打ち込む場合や、既存の杭・ブロック塀が正しい位置にあるか再確認する場合があります。昔の杭が実際にはずれていることも珍しくなく、ここで隣地所有者の理解を得ながら正規の位置を再設定する必要があります。
•合意が得られれば、その地点を境界点として「ここが正式な境界」と認定します。
2.意見の対立があった場合

•隣地側が「昔からここが境界だと聞いている」など、口約束や過去の不明確な取り決めを持ち出すこともあります。測量士は公図や登記簿、過去の航空写真など可能な資料を総動員し、事実確認と説得を行います。
•合意が得られない場合は、弁護士などの専門家を交えて話し合いを続けたり、最終的には「境界確定訴訟」を視野に入れたりすることになり、時間と費用が膨らむ恐れがあるため、事前の根回しや説明が重要です。
3. 費用と期間の目安
境界確定測量の費用は、敷地形状の複雑さや測量士の報酬体系、隣地所有者の数などによって大きく変わります。一般的には数十万円~百万円超になることが多く、広大な敷地やややこしい境界が絡む場合はさらに高額になるケースもあります。
1.期間の一般的な範囲
•スムーズに進めば、1〜3か月ほどで測量と立会い、合意形成まで終えることが可能です。ただし、隣地所有者との日程調整や意見のすり合わせが難航すると、半年以上かかるケースもあります。
•市街地で敷地が細分化している地域や、歴史的経緯で複数の権利者が並存する場合など、1年以上にわたって合意が得られないケースも存在します。
2.着工前の準備

•売却のスケジュールを考えているなら、測量士への相談はなるべく早めが鉄則です。内覧や買主の交渉が進む段階で「境界がまだ確定していません」となると、買主が二の足を踏む可能性が高く、売却期間が長引きやすいです。
•もし売却活動と平行して測量を行う場合でも、買主が前向きになった段階で「測量にあと何か月かかる」と説明すると、値下げ交渉や契約見送りのリスクが増すため、事前に終わらせておく方が有利に働くことが多いでしょう。
書類作成・法務局登記
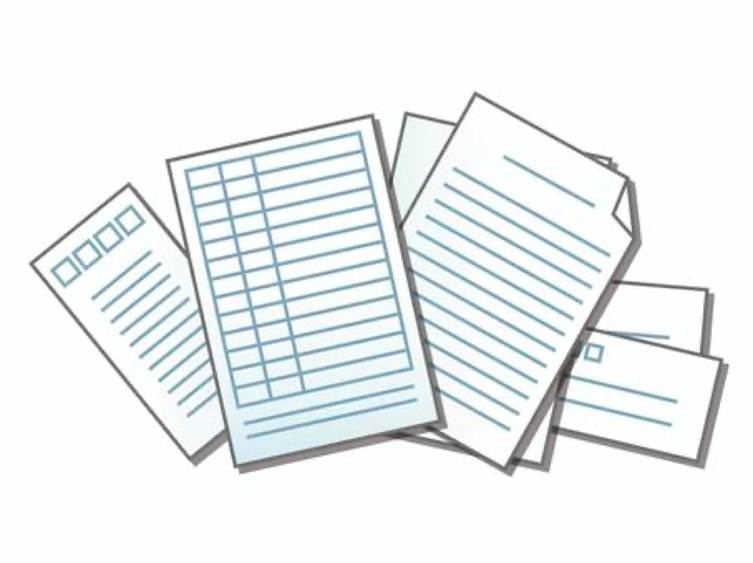
測量を行い、隣地との境界が明確化すれば終わり…というわけではありません。実測結果をもとに、境界をはっきりさせる公的書類を整備し、必要に応じて法務局で地積更正登記や地図訂正を行うことで、登記情報を最新かつ正確な状態にアップデートする必要があります。
これにより、買主も公的証拠を確認でき、ローン審査や売却手続きにおける不安が解消されるのです。
1. 境界確定書・隣地承諾書の作成
測量後には、測量士や土地家屋調査士が「境界確定図」や「境界確認書」「隣地承諾書」などの書類を作成します。これらには以下の情報が盛り込まれています。
•どの地点を境界としたか
隣地との境界点の座標や測量データ、境界杭の位置など。
•境界を定めた根拠
公図や登記情報、現地の痕跡(旧杭)など、総合的に判断した証拠。
•当事者の署名捺印
隣地所有者と売り主が「この線で合意しました」という形で署名し、法的に有効な合意の証拠とする。
公的な証拠としての意義も大きく、後で「違う」と言い張ることが難しくなるため、紛争防止効果が非常に高いです。
2. 法務局での地積更正登記や地図訂正
地積更正登記とは、測量により実測面積が公図の面積と食い違う場合に、正確な数値へ訂正するための手続きです。例として、公図上100m²となっていた土地が実測だと98m²だった場合、法務局に地積更正の申請を行い、新しい面積を登記簿に反映させる必要があります。
1.地図訂正との違い
地図(法務局備付地図)や公図の訂正が必要な場合、地積更正登記とは別の手続きが行われることもあります。地域や法務局の運用によって異なるため、土地家屋調査士に相談して最適な手順を踏むことが望ましいです。
2.売却時のメリット
登記上の面積が実測と一致すると、買主が担保評価を行う際にもメリットがあります。もし面積が増えた場合は評価が上がり、減ったとしても「実態に合わないまま取引する」というリスクが消えるため、契約不適合責任で揉める可能性を減らせます。
3. トラブルがあった際の対応

万が一、測量結果に納得しない隣地所有者がいて合意できない場合、境界確定訴訟という裁判手段に進むケースがあります。これは裁判所が境界を最終的に判断する仕組みで、時間と費用がかかる重いプロセスです。
•費用と期間
弁護士費用や追加の測量費などで数十万円〜数百万円に及ぶ可能性があります。期間も半年以上、長い場合は1年を超えることが珍しくありません。売却を急いでいる売り主にとっては大きなデメリットですが、隣人が全く歩み寄らないと選択肢が限られてしまいます。
•調停などの選択肢
訴訟に行く前に民事調停などで折衷案を模索するのが一般的です。調停委員を間に挟んで話し合い、妥協点を探ることで合意に達するという場合もも多くあります。
不動産売却の際に境界が不明確だと、買主がローン審査を行うときに担保評価が下がるだけでなく、「越境しているのではないか」「面積が想定より少ないのでは」といった不安から、買付申込みを敬遠される恐れがあります。
そこで、境界確定測量によって隣地所有者との合意を得た明確な境界を示せば、トラブル発生リスクを大幅に減らし、適正な価格でスムーズに契約成立へと導くことが可能です。
測量士へ依頼してから実測、隣地立会い、合意形成という一連の流れには、数十万円以上の費用や数か月程度の時間が必要になる場合が多いものの、将来的な値下げや契約不適合責任のリスクを考えれば、投資価値は十分に見込めます。
測量結果をもとに作成する境界確定書や隣地承諾書は、公的にも説得力の高い証拠書類となり、さらに地積更正登記を行えば法務局の登記情報を正確化でき、買主が安心してローンを組めるメリットも得られます。
万が一隣人が協力的でなかったり意見対立が深刻な場合は調停や訴訟も想定されますが、そこまで至らないよう早めに測量を開始し、隣地所有者とのコミュニケーションを丁寧に行うことが成功の鍵です。
◯あわせて読みたい記事
不動産売却の手続きとは?必要書類の種類・取得方法・特例を紹介
まとめ:測量でスムーズ売却と高評価確保
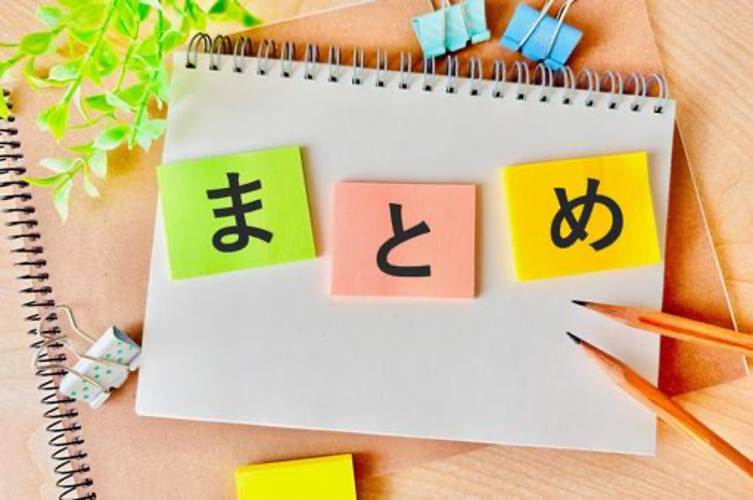
不動産の売却をスムーズに進めるには、境界確定測量による正確なデータと、隣地所有者との明確な合意形成が欠かせません。測量士(または土地家屋調査士)に依頼し、現地での実測と隣人立ち会いを行って境界を確定させれば、「越境していた」「面積が違う」などの後日の紛争リスクを大幅に減らせます。
さらに、境界確定書や承諾書を作成して法務局に地積更正登記を行えば、公図と現況を一致させて不動産情報を正確にアップデートできるため、買主のローン審査も通りやすくなるでしょう。
もし反対や意見の衝突が生じて合意できない場合は、調停や裁判を視野に入れる必要がありますが、多大な費用と時間がかかるため、事前の話し合いと専門家(弁護士や司法書士)のサポートが重要です。境界確定測量は一見面倒に思えるかもしれませんが、結果的には売却価格の維持や成約スピードの向上につながる大きなメリットがあります。
売却活動を円滑化し、買主に安心感を与えるためにも、境界不明の不動産を所有しているなら早めに測量士へ相談し、境界を明確にしてから市場に出すことをおすすめします。
◯あわせて読みたい記事